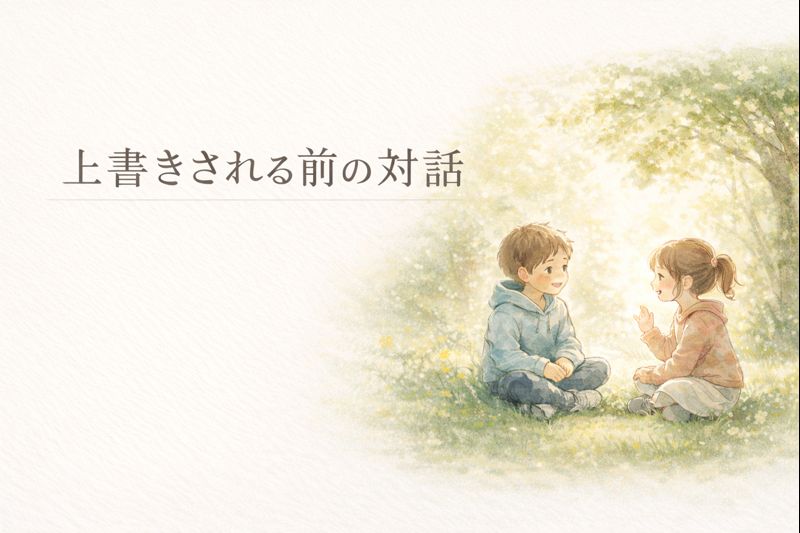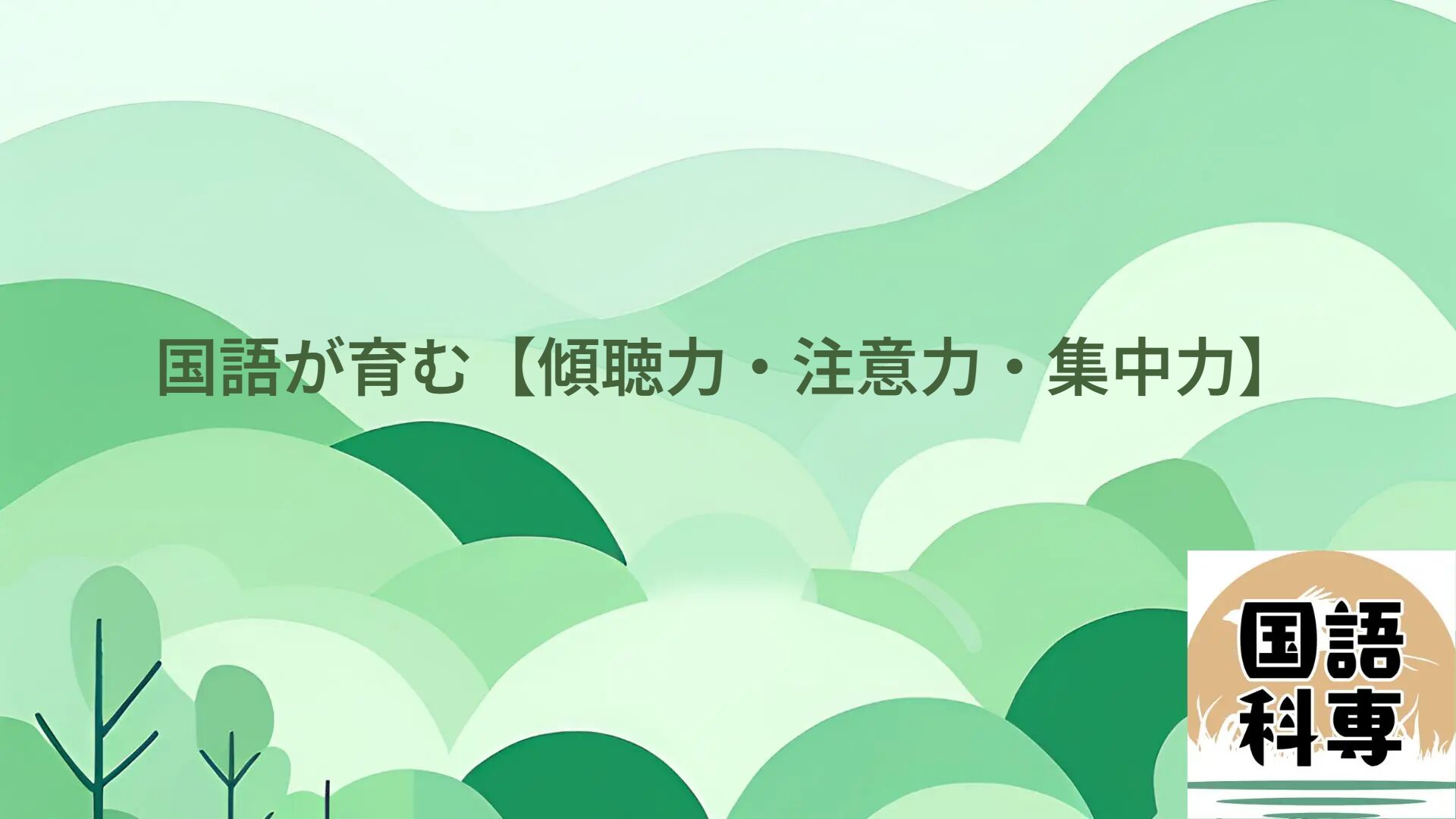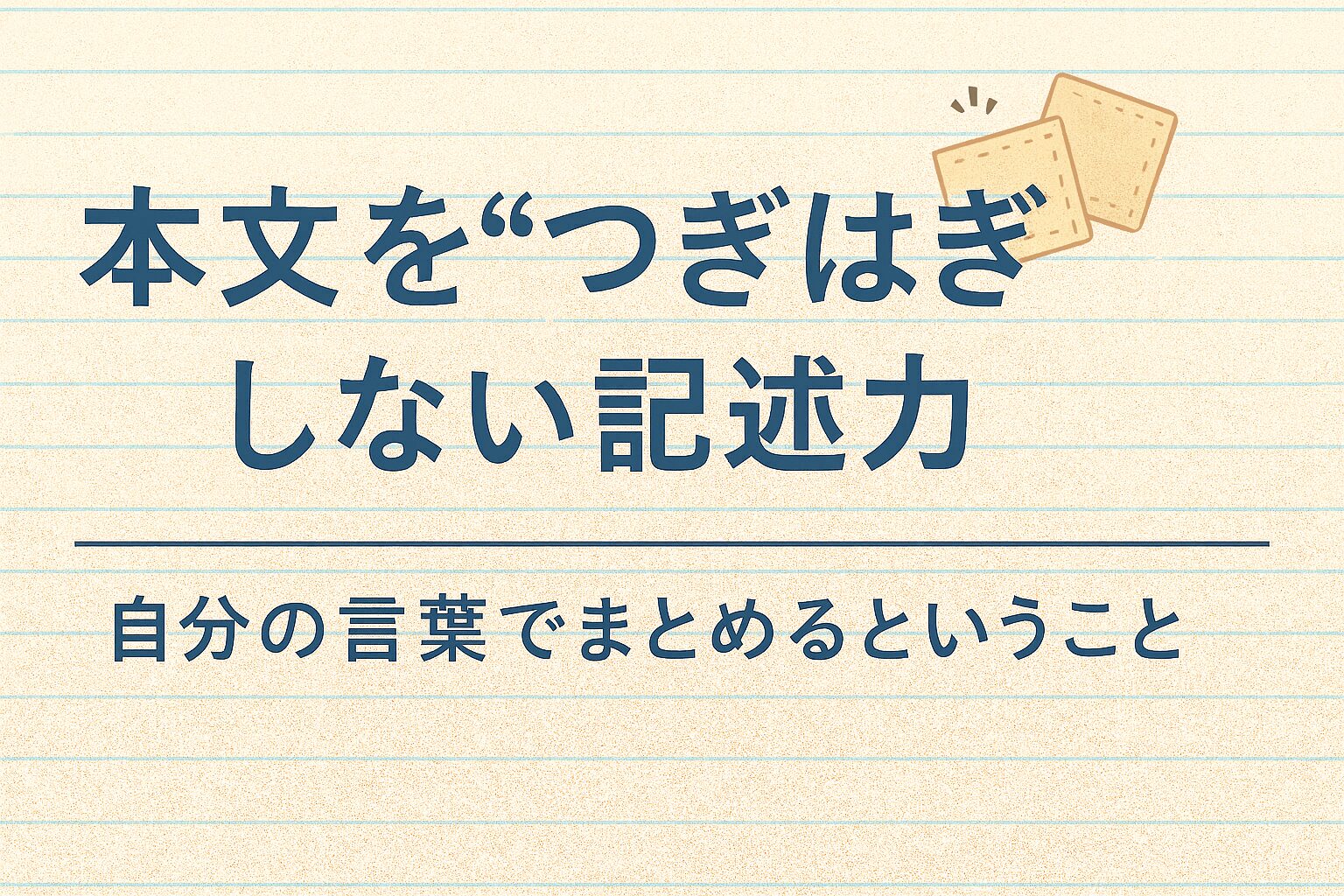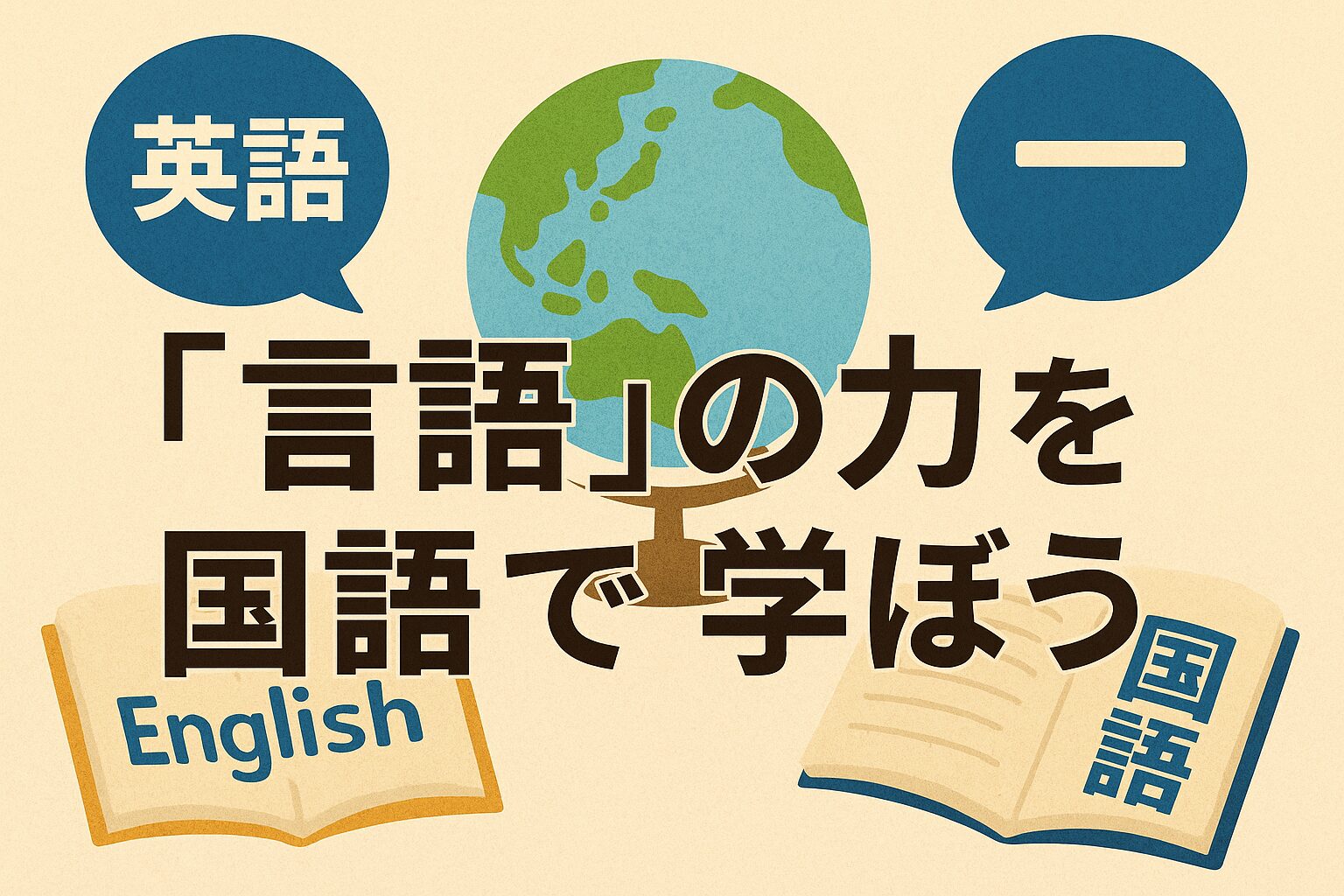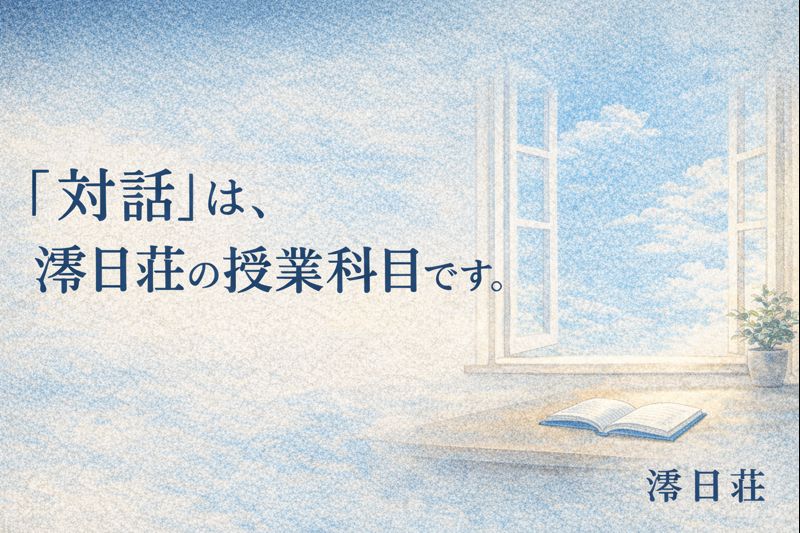なぜ勉強は嫌われるのか ― 学びの本質を探る三つの視点
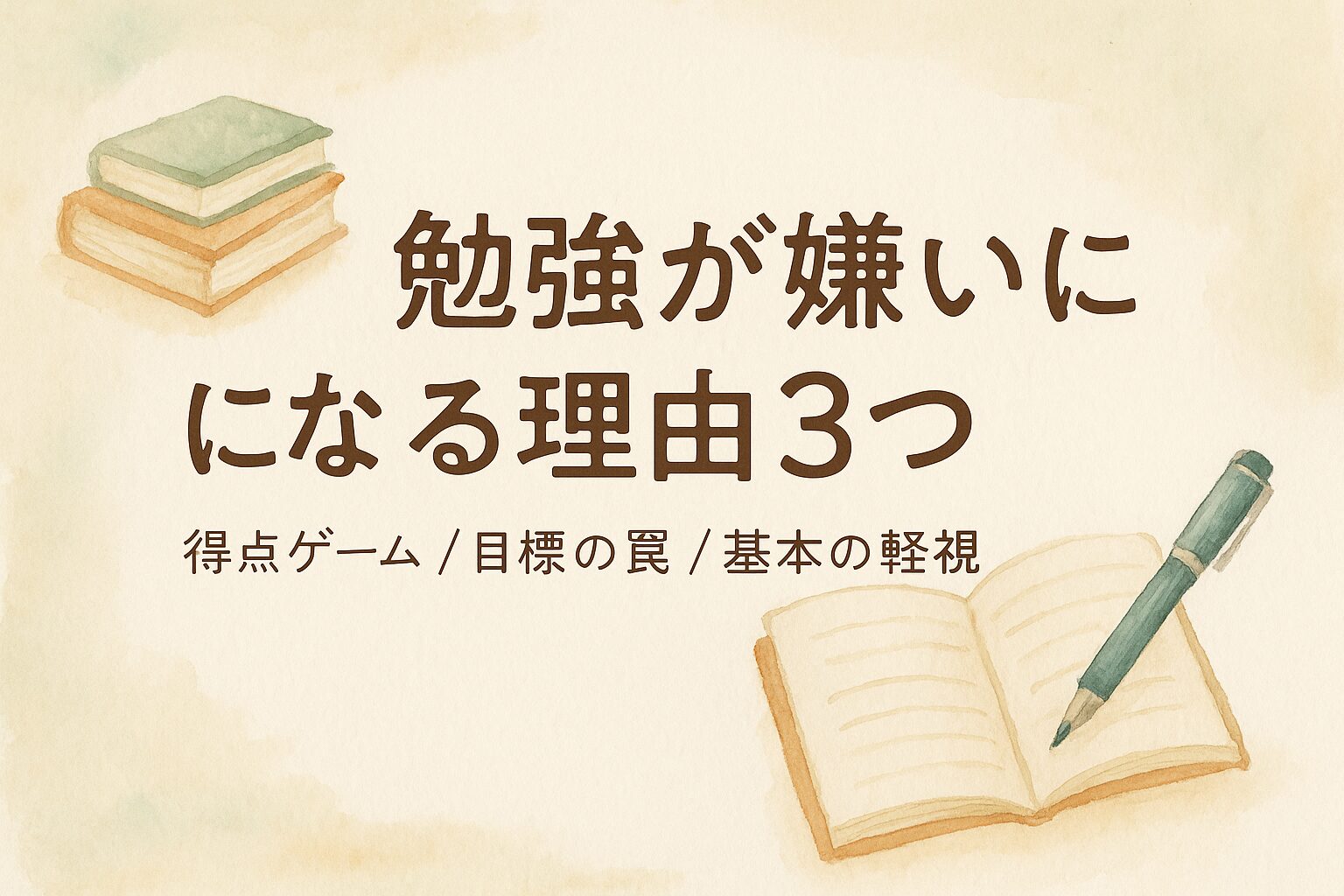
勉強って、どうして嫌いになってしまうのでしょうか。
点数を取っても楽しくない、やらされている気がする、応用はできてもなぜか好きになれない…。
そんな声を多く耳にします。
以前も「勉強が嫌いな理由とは?」というタイトルで学びの本質を検討しましたが、今回はもう一歩この点について深めてみようと思います。
もちろん嫌いになるには種々多様な原因・理由があるはずですから、ここですべてを挙げることは不可能ですけれど、最近の傾向として代表的だと感じるものを取り上げてみます。
三つのポイント
日常的にお子さんや生徒さんと関わっていて、強く感じるのは以下の3点です。
- 学びが得点ゲーム、ものさし化すること
- 「目標」による学びの限定
- 基本事項など土台の軽視
得点ゲーム
冒頭で触れた以前の記事でも述べましたが、現代に至り、勉強(や社会・人々)が目に見える結果を重視するようになりました。
しかし、現実には目に見えないまま利用しているものや、原理の分からないまま受け入れているもの、そのいずれにさえも気づいていないものが数多く存在しています。
そして人はそのことを本能的に理解しているのではないかと考えています。
それゆえ、「目に見える」結果の明瞭さによって勉強に取り組みやすいと同時に、その同じものによって違和感を抱くことになるのではないでしょうか。
これが、勉強デキるけれど勉強ギラいな子がたくさんいる一因だと思います。(もちろん勉強がデキなければ楽しくないので、普通にキライになることでしょう。)
「目標」の罠
次に、達成目標を重視することからくる勉強嫌いもあります。
目標を追い求めれば求めるほど、そこへ達するための手段としての「勉強」は駒に過ぎなくなります。
もっと効率的に、もっとコスパ・タイパよく、もっと手軽に目標へ達することができたならば、それ以上に素敵なことがあるでしょうか。
こうして学習内容そのものよりも、そこから得られる収穫・効果に意識が集中していき、勉強はさらに手段となっていきます。
手段ばかり深掘りして扱っていては目標に到達することができないので、学習内容の探究は制限されます。
また、目標を達成した他者の語るコツやハウツーを用いる便利さをより強く感じますから、学び(発想・思考)の透明な画一化がおのずと進行します。
目標そのものや達成者が示してくれる「必要」以上に学ぶ意義が薄れ(「型」に沿ってやれば点は取れるなど)、各科目において多様な面白さは目減りし、つまり勉強が楽しくなくキライになることでしょう。
加えて目標によって自身が縛られるため、勉強が義務となることもキライに拍車をかけます。
基本の軽視
どんな教科書でも、新しく学ぶ範囲の冒頭はとても易しい内容から入っていきます。
理系の生徒さんでなくてはほとんど触れない数学Ⅲでさえ、各章の冒頭は土台となる定義や考え方の提示をしていて、その中身自体は時間を掛ければ小さなお子さんでも理解できるものです。
しかし、どの科目でもその土台の説明や提示がすぐ済むがゆえに、引き続き活用や応用の問題が導入され、見かけ上の難易度が急上昇しがちです。
基本や土台が含み持つものとなじむ前に応用問題へ進んでいくと、理解や活用の実感が乏しく、「できても分からない」現象が出てきます。
どうして基本部分に時間が割かれないのかについては、主体を分けて考えてみると面白いかもしれません。
自分
学習者としても、基本部分は教科書の一部だし、一読して理解できたとすれば、自然とページをめくってしまうでしょう。
紙幅やカリキュラムが限られているから、という物理的な理由もこれを促進します。
ところが、応用問題でつまずいたとき、次の一手を基本事項の内実から導くことができません。
解くべきはその応用問題ですから、応用の仕方をいろいろと調べたり尋ねたりして仕入れ、どうにか解き進めていきます。
この中で基本事項の本質が分かってくる場合(多少面白くなる)もあるし、そうでなく「型」によってクリアしていく(別に面白くない)場合もあります。
だからといって基本事項のページを何度も読めばよいというわけでもないので、そもそも基本は習得が難しいものなのかもしれませんね。
他者
学校や塾において、どのくらい基本事項が重視されるかは、教える側の理解の程度に依存すると考えられます。
教える側がどのくらい深めたか、その前提として、どのくらいその科目に興味関心を抱いて取り組めたかが、教え方にそのまま響いてきます。
このとき、能力を高めることに軸足を重く置くと、どうしても応用に傾くことになります。
そして、難問は解けるけれど基本は危ういという生徒さんも生まれることになるわけです。
このような生徒さんは、問題が解けて得点ができたとしても、内容が自分のものになっていないから、特に好きではないという例もよくあります。
勉強キライは楽しさへの橋渡し
今回は勉強が嫌いになる原因・理由として、3つの大きな点を検討してみました。
もしかしたら、あなたもどれか当てはまっていましたか??
当てはまる理由があったとしたら、それは学びを手放す理由ではなく、見直すきっかけかもしれません。
嫌いの背景を知ることから、本来の学びの楽しさへつながっていきます。