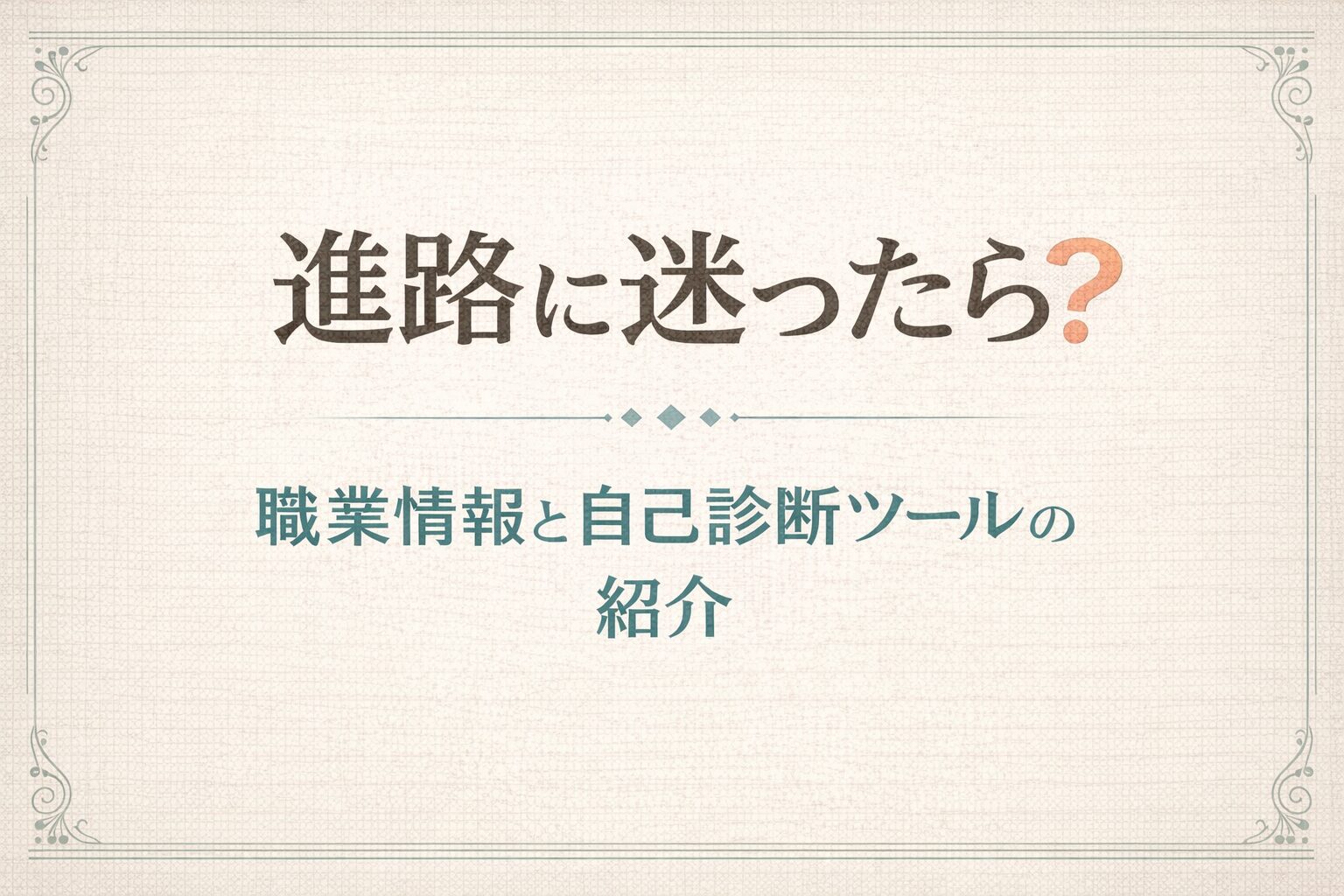生徒さんと話した日々④:「診断はレッテルですよね」Dさん

このカテゴリーでは、これまで一緒に学んだ生徒さんについてお伝えします。
もちろん名前は伏せていますし、細部はぼやかしてありますが、
どんな人物だったのかはご理解いただけるよう心掛けています。
今回は、自分自身をするどく見つめていたDさんです。
出会いと、Dさんの第一印象
Dさんと出会ったのは、高校二年生の、進路について本格的に考え始めていた時期だったと記憶しています。
年齢のわりに落ち着いた雰囲気があり、話し方もどこか大人びていました。
早い段階で、Dさんはご自身が自閉症スペクトラムと診断されていることを、特別な前置きもなく語ってくれました。
そして、その診断名について、
「社会の中で、こういう人間を扱いやすくするためのレッテルみたいなものですよね」
と、淡々と話していたのが印象に残っています。
その言葉には、諦めや怒りというよりも、状況を一段引いたところから見つめているような冷静さがありました。
一緒に取り組んだ学びの時間
Dさんとは、主に進路に関わる話題を中心にやりとりをしていました。
学力面の補強というよりも、「どこへ進むのが自分にとって自然か」を考える時間が多かったように思います。
自身の不登校経験から、社会的マイノリティ、ユニバーサルデザインやバリアフリーといった分野に関心を持っていて、それは単なる社会貢献への関心というより、
「誰かが排除されにくい構造そのもの」
に目が向いているように感じられました。
学びの話をしていても、いつも視点が個人に閉じず、
社会や空間、仕組みのほうへとひらいていくのが、Dさんらしいところでした。
診断名と、自分の距離感
Dさんは、ご自身の状態について必要以上に語ることはありませんでした。
ただ、診断名があることで、
・説明を省ける場面があること
・一方で、先に理解された気になられてしまうこと
その両方を、よく分かっているようでした。
だからこそ、
「その名前で自分を説明しきらない」
という距離感を、自然に保っていたように思います。
このあたりの感覚は、年齢以上に成熟している印象を受けました。
芸術と進路の選択
もともと芸術への関心が強く、最終的には美術大学への進学を選ばれました。
ユニバーサルデザインへの関心と、芸術という領域が、Dさんの中では無理なく結びついていたように感じます。
表現やデザインを通して、
「誰かを矯正する」のではなく、
「最初から排除しない形をつくる」。
そうした方向へ自然に目が向いていったのは、
Dさん自身のこれまでの経験とも、どこかでつながっていたのかもしれません。
いま、振り返って思うこと
Dさんは、自分を理解しすぎないことで、
かえって自分の足場を保っているような方でした。
思えば芸術も個人の感覚から生まれるのに、広く受け入れられ得るものです。
彼女はきっとこれからも、名前や枠に回収されきらない場所で、
ご自身の感覚を頼りに歩いていかれるのだと思います。
応援しています。