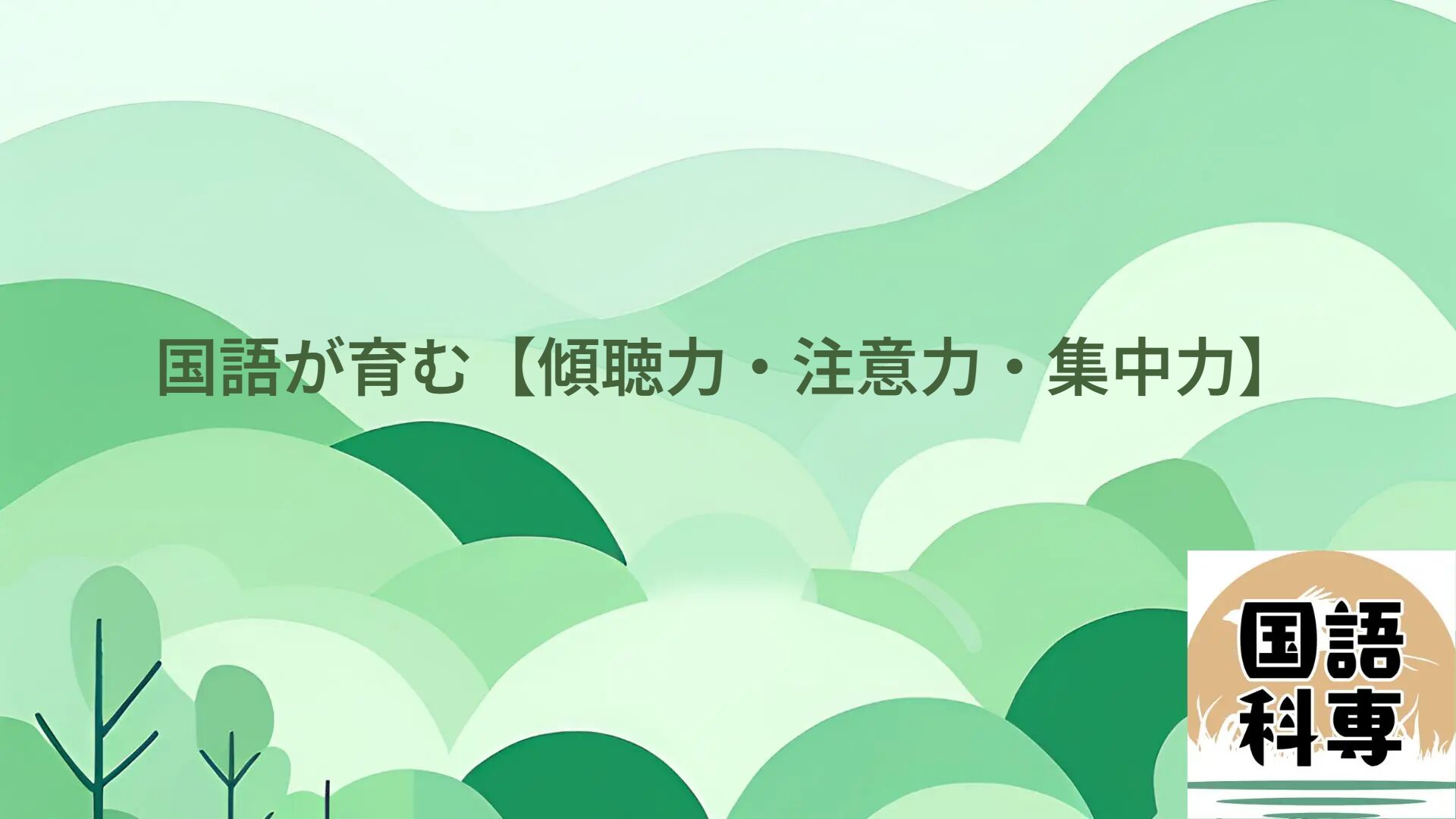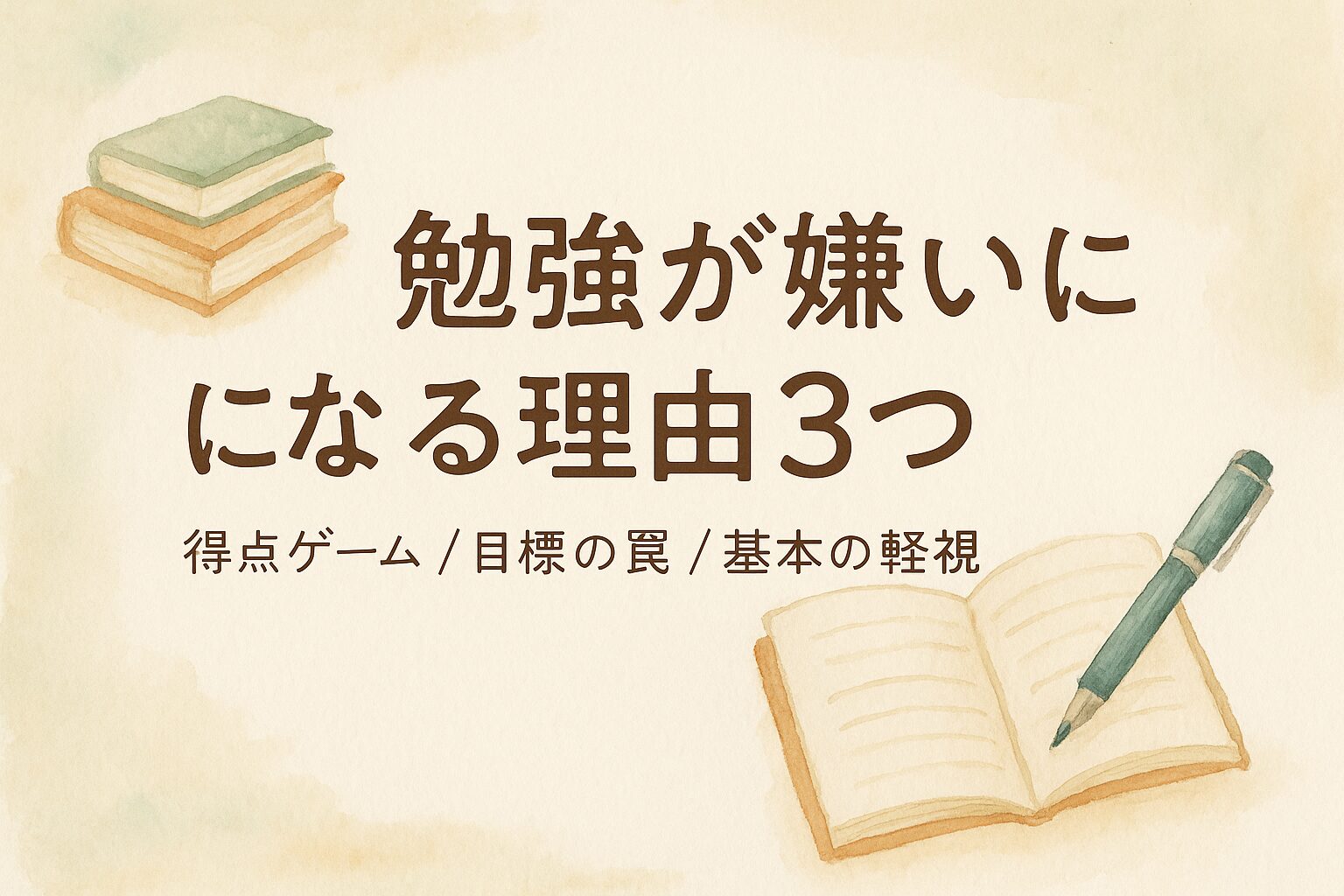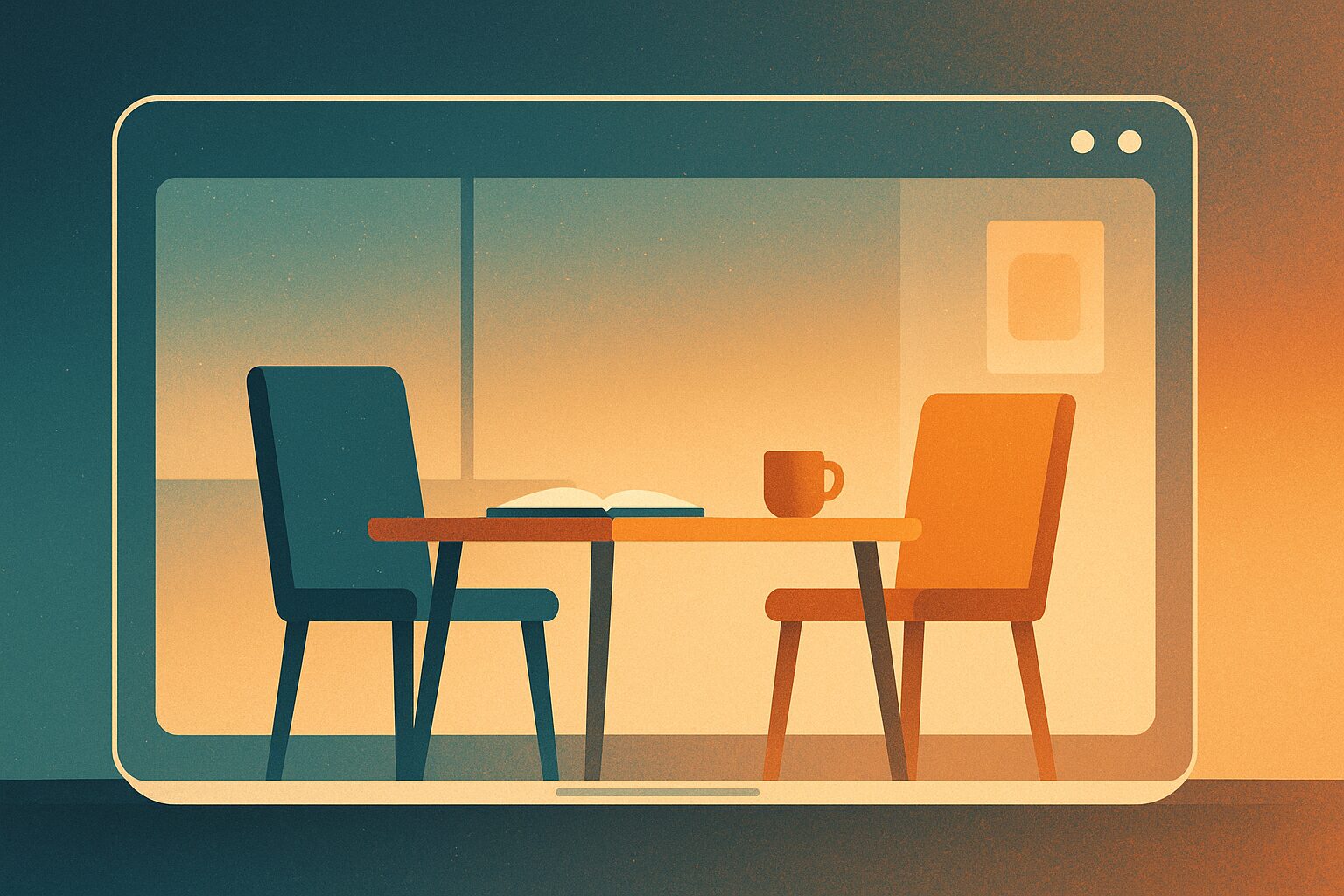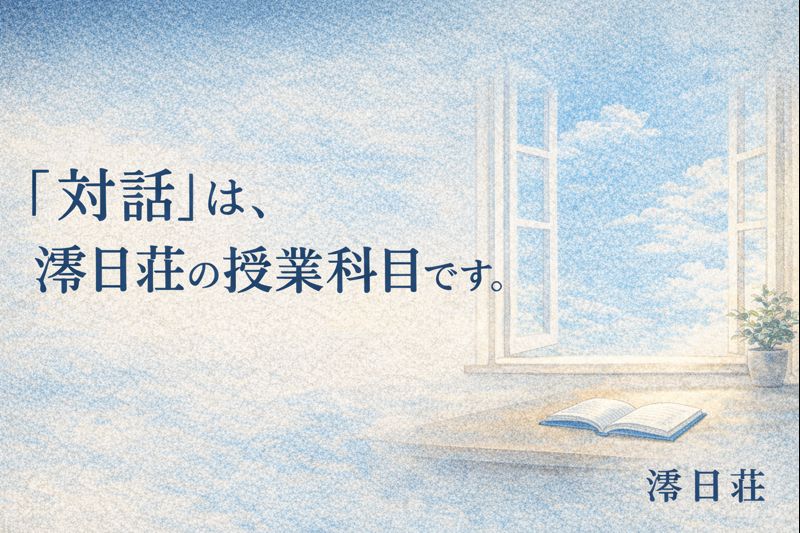学びとは ― 響き合いが生まれる場所
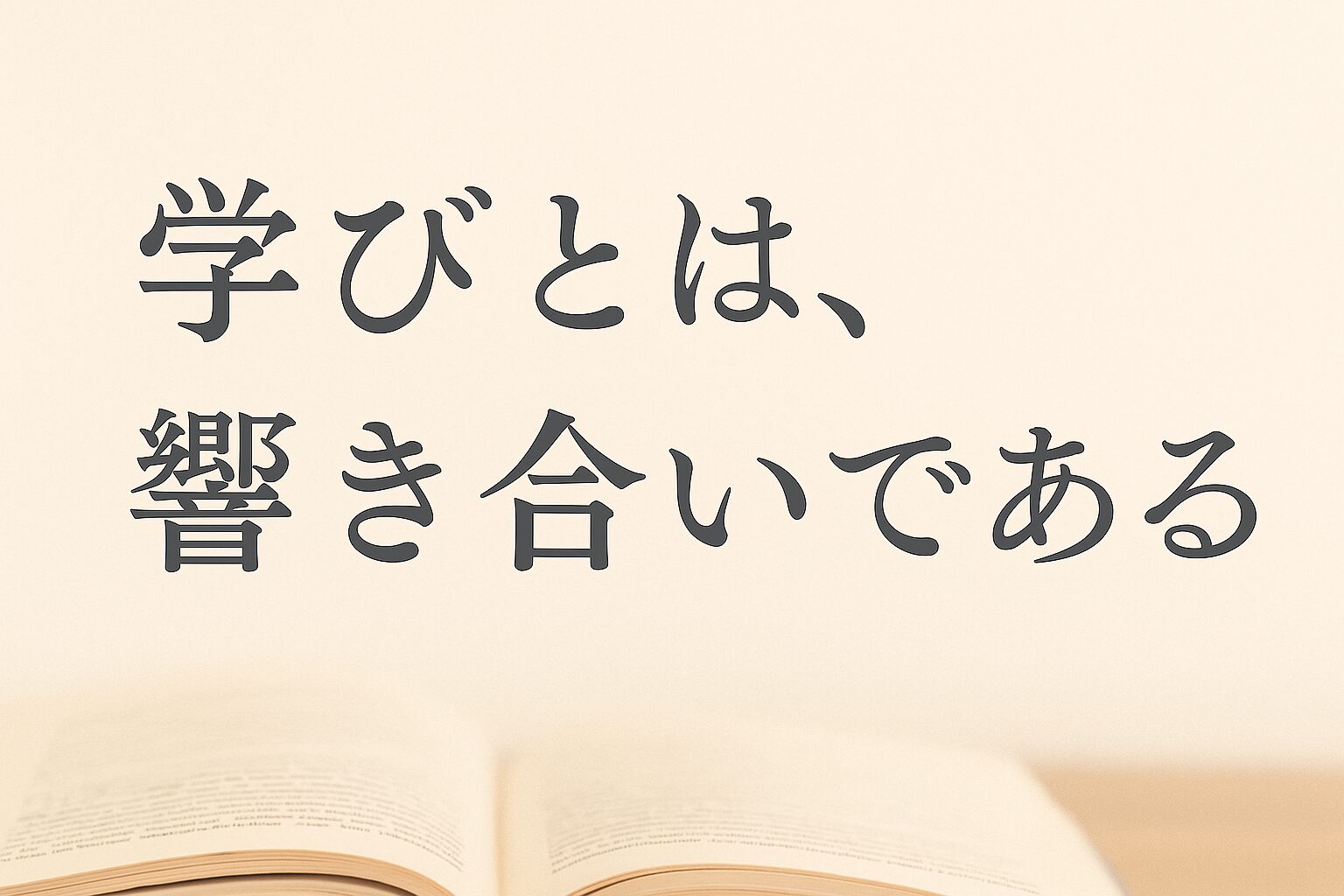
wowja
Contents
学びとは ― よくあるイメージから
一般的に、学びや学習は次のようなものとしてとらえられることが多いです。
- 科目や対象の内容を記憶・適用・反復する
- 内容を身に着けること、その内容の探究
- 教わること、マネすること
しかし、学びにはもっと幅広い意味や意義が含まれていると考えています。
これを示す裏側からの根拠として、たとえばたくさんの知識や情報を脳に記録していても、思慮が浅いとされる人は存在します(決して批判しているのではありません)。
その反対に、知識はほとんど持ち合わせていなくとも、深い知恵を有している人もいます。
学びの広がり
このことから、内容やその活用、量、行為に限定されない「学び」があるはずだと推論できないでしょうか。
すなわち、
- 興味関心など自己理解・感得
- 表には見えてこないはたらき・作用の知覚
- 自己の表現そのものとしての学び
などととらえることができるかもしれません。
いま挙げた「学び」の要素たちは、無理やりに作り上げることが難しく、あえてそうすることは大きな負担や屈折につながります。
あるいは、かえって学びを型にはめてしまい、他の可能性を閉ざすことにもなりかねません。
以上から、ここに挙げた学びの要素たちが本来的な「学び」であるとするならば、それは強いて学ぶことが不可能な事柄だということができそうです。
響き合いとしての学び
したがって、自分とどのような響き合いが生まれるかを知る機会として、学びを意識することを提案したいと思っています。
何かを知ったり、身に着けたり、できるようになったりという発想を控えて、自分がどのように感じるか、その事柄を貫いているはたらき・観念はどのようなものかなどを自分の目で見つめていくこと。
そうして学びがその範疇を飛び出すことで、強制的に作り出すことができない自己表現としての学びが育まれるのではないでしょうか。
ABOUT