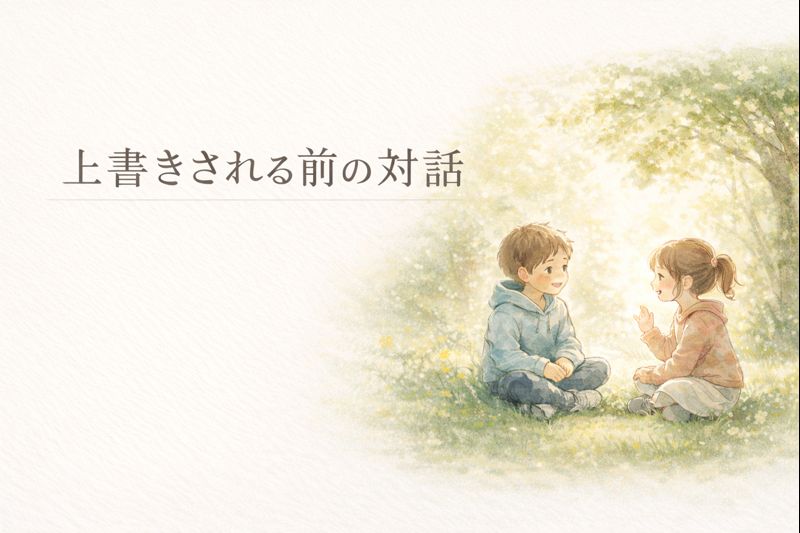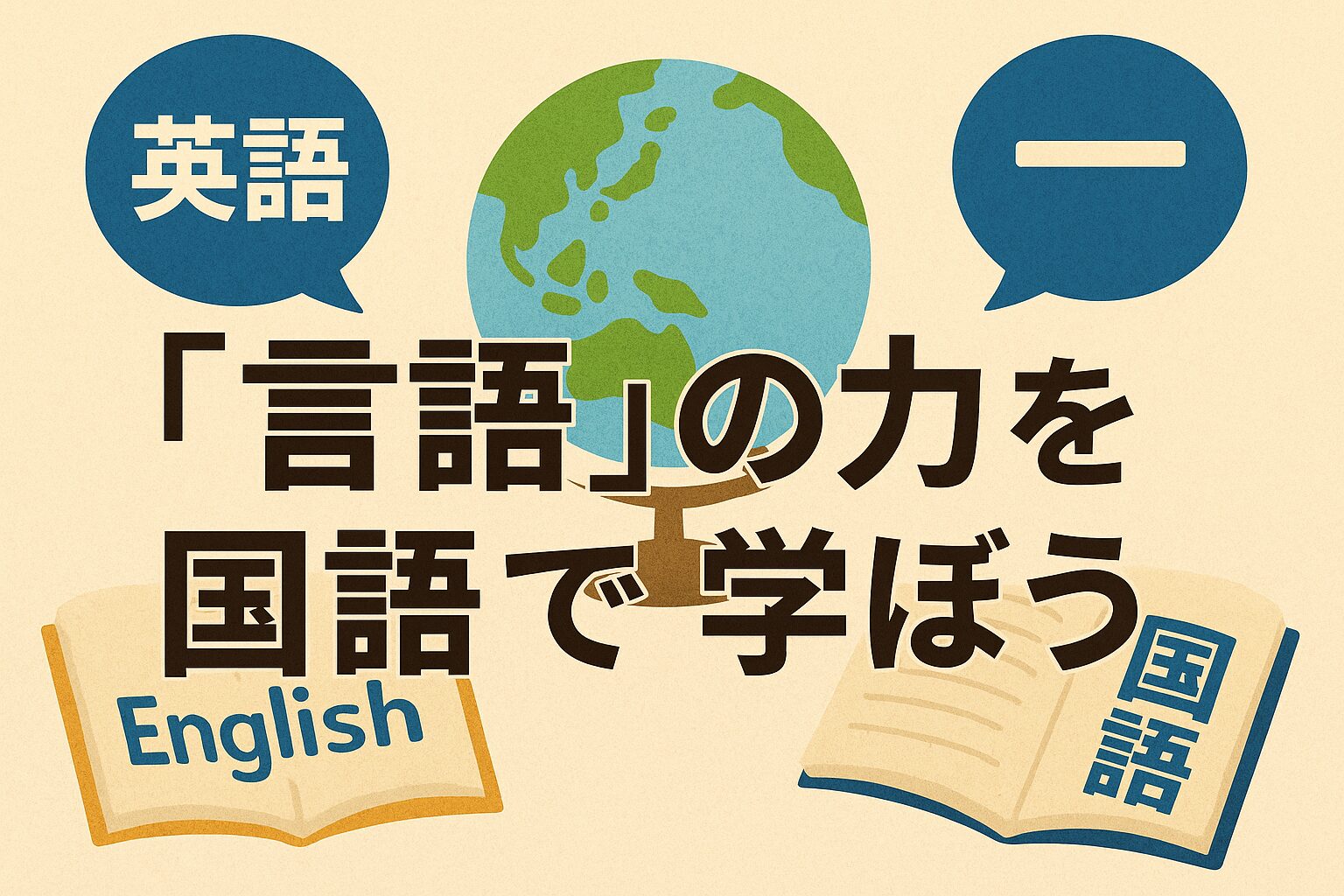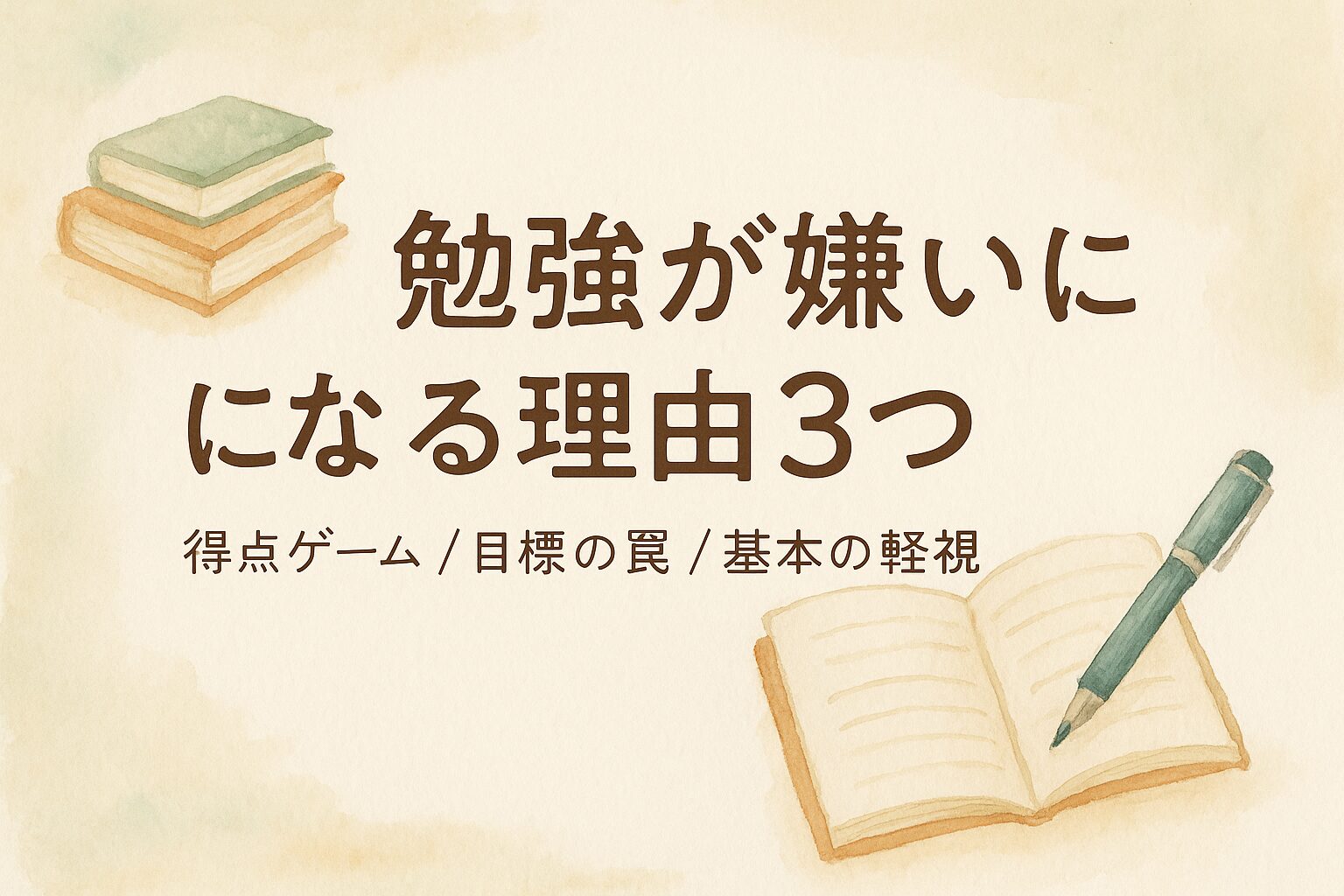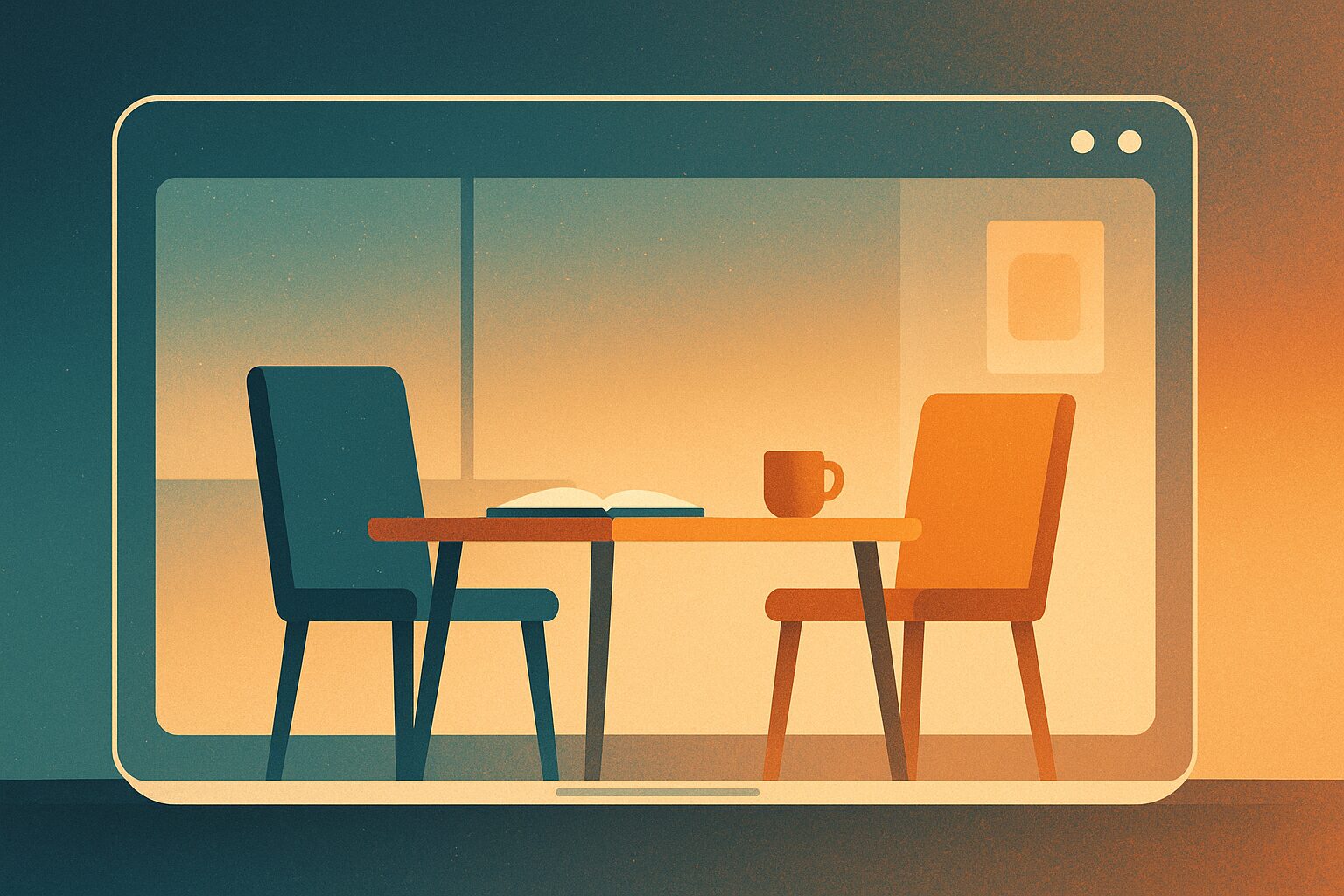推薦入試の本質を見つめて──変わりゆく入試と、これからの学び

ふり返れば学力偏重といわれ、誰もがとにかく成績・点数を伸ばして「良い」大学へ入学することを目指していた時代がありました。
最近ではそうした動きに対する反省や評価に基づいて、いろいろな大学や企業においても、生徒さんや学生さんの成績表ばかりを重視せず、人物や経歴・活動実績などに焦点を当てた入試や入社試験が増加しています。
そこで、とりわけ大学入試について、推薦入試の本質とその「対策」の実質を見ていきます。
推薦入試って何?──その本質と広がり
総合型選抜・学校推薦・自己推薦など、学科試験(ペーパーテスト)の点数のみで合否を決めるのではない入試形式を導入する大学が増えています。
このようないわゆる推薦入試では、生徒さんの人物全体を総合的に評価して入学を許可するかどうか判断するとされます。
その評価のため、経歴や活動実績、興味関心の所在、将来の展望・希望(・野望)など広く大学側が情報を求めます。
同時に、推薦とはそのポストや募集枠に適切な人物だと推挙する行為ですから、推薦者が判断しやすいよう、大学側もどういう人材を欲しているのか具体的に提示しています。
この具体的な提示を確認して、自身の望む学びができる大学を選び、受験生が推薦入試に向かうことになります。
“受かるためだけ”の推薦対策から抜け出すには
以上のように、大学側が求めるものと、受験生が目指すものが一致することによって、然るべき学校へ然るべき生徒さんが入学することを意図したのが推薦入試です。
大学が一定の型を提供し、そのように成型された人間を世の中に送り出すだけの場所でないならば、あくまでスタートは生徒さん自身の興味関心や望むことであって、大学が求める条件に見合うかどうかはその次に検討されるべきものです。
ある大学がこのような人材を募集しているから、自分もそこに当てはまる経歴・実績などを形作ろうという「操作」は本末転倒になりかねません。
受験生の人物全体は、学業や日常生活、もともとの素質、人間関係その他無数の事柄から成立しています。
その中で推薦入試に使いやすい部分を切り出してくることは、学力のみ抽出して勝負していた時代と同質の発想に陥る可能性があります。
ですから自分への理解を深めることが根幹であり、それを離れた推薦入試「対策」は本質的に存在しないと考えています。
教育が目指す“真の多様性”とは
ここで、私たちが教育を通して何を志向しているのかという問題に直面します。
かつては国を強くするための頭脳を育成することが目的でしたから、さまざまなタスクをこなすことができる、いわゆる能力の高い人間を産み出すことが軸にありました。
そのためにとにかく学力に優れた人材を求め、さらに難しく複雑な作業を担えるよう教育を重ねました。
しかし時代が変化するとともに、人間が取り組むはずの事柄は頭脳を使うものに限られず、身の回りに想像できるもの、さらにそれ以上に多様なものであることが理解されてきました。
この状況に対応して、教育も単なる人材育成にとどまらず、この世界に真の多様性を保障する役割を負うようになってきています。
その人自身を伸ばす発想
したがって、教育はもはや(本当は昔からですけれど)教育に携わる人だけが担うものではありません。
家庭や日常での生活、学校・学業、部活動、趣味、遊びなどお子さんや生徒さんを取り巻く多様なあらゆることが人物形成に寄与していて、そうやってできあがる「人物」を評価しようという入試形式(推薦入試)が拡大しているからです。
この流れは、個々人の特質・特性が社会や未来を形成していくのだ、という私たち自身による力強い宣言だと理解することもできます。
すなわち改めて、推薦入試のため資格取得に実績作りに、対策に対策を重ねた受験活動は、上記の多様性を志向する発想と相いれないことが分かります。
本当に個性豊かで枠にとらわれない実力を持つ人物を育てたいのなら、ただ生徒さんが自分自身を表すことができるよう、学びを支援したり、日頃から見守ったり、応援したりする以外にないということになります。
対話を通じて育まれる、思考と人格
生徒さんが自分自身を表現するための支援の仕方にはいろいろあると思いますが、中でも対話することは大変おすすめです。
いずれかが何かを教えるのでもなく、押し付けるのでもなく、なだめるのでもなく、共感するのでもなく(もちろん共感することも大切ですが)、ただ話をして理解すること。
これらすべての行為が、自分自身や他人を受け入れることにも繋がります。
その段階に至れば、もともとの人間(生命)の力は大変なものですから、生徒さんは自分で自分の道を築いていくものです。
最初のうち自分の考えがまとめられず、口頭でも言葉が出てこない中学生の生徒さんがいました。
漢字や記述問題など国語の勉強を継続し、なるべくお話も多めに実施していたところ、最終的に授業時間の半分以上を生徒さんからのお話に費やすまでになりました。
その生徒さんは現在、海外へ留学しています。
澪日荘の特徴
以上のような考えで、当方では国語を中心に、対話を積極的におこなうスタイルで学びを支援しています。
「対話科目」としての国語という記事でも書いたように、国語はおのずと自分や他者との対話を促すことになる科目です。
加えて、日常生活や悩みなど、タブーなく限定なくどんなお話でもOKという形で、お子さん・生徒さんが自分自身の道を見出していくお手伝いをしています。
対話が本当に成立してくると、うまく言葉にはしづらいのですが、お子さんや生徒さんの雰囲気が大きく変わってきます。
もしご家庭や学校でなかなか対話が難しいという場合には、こちらで少し一緒にお話しする機会を設けてみませんか。