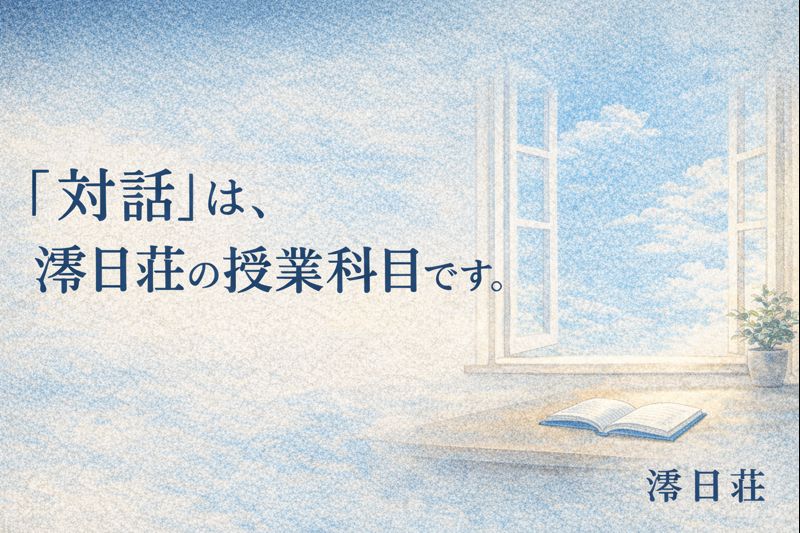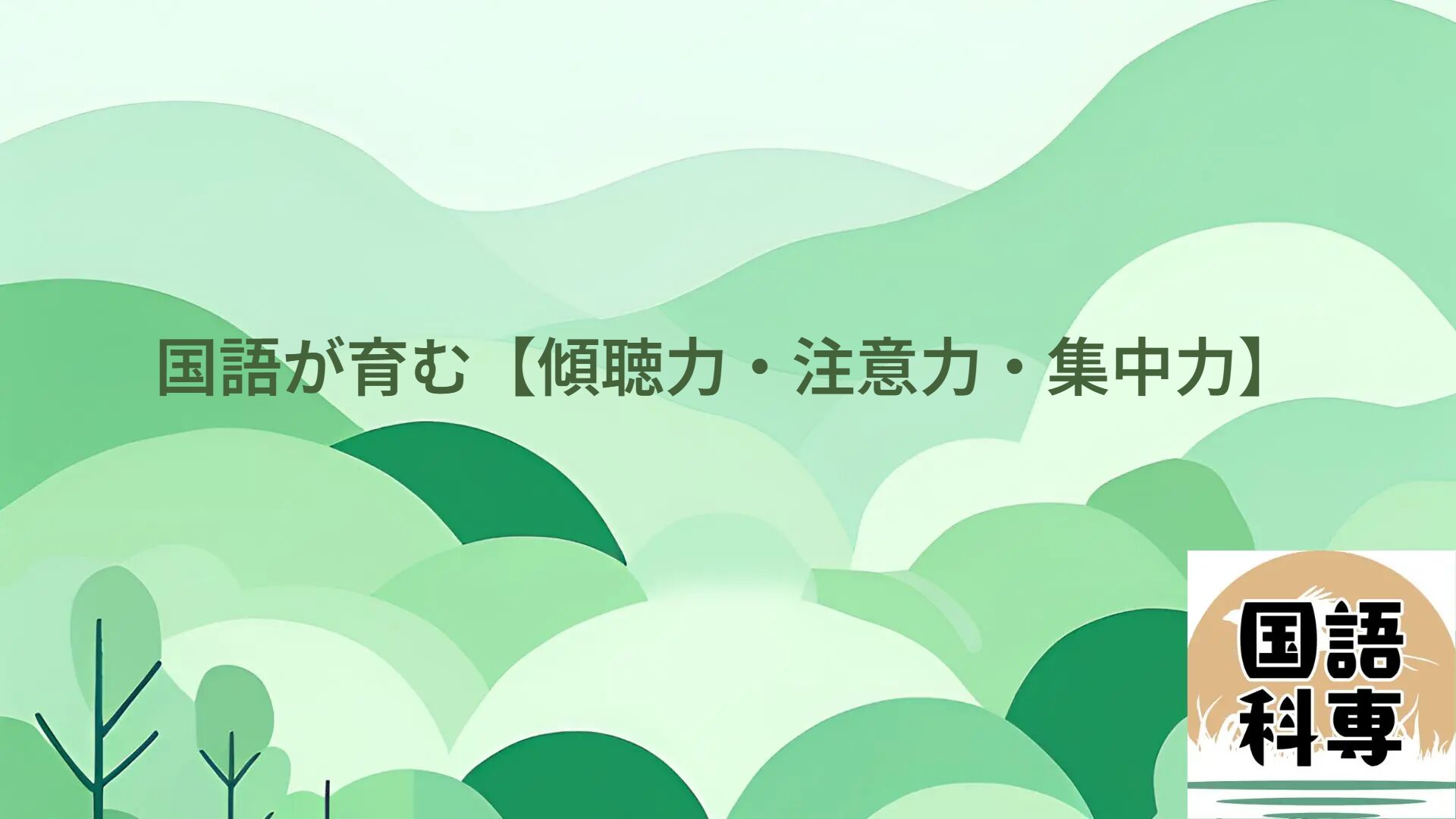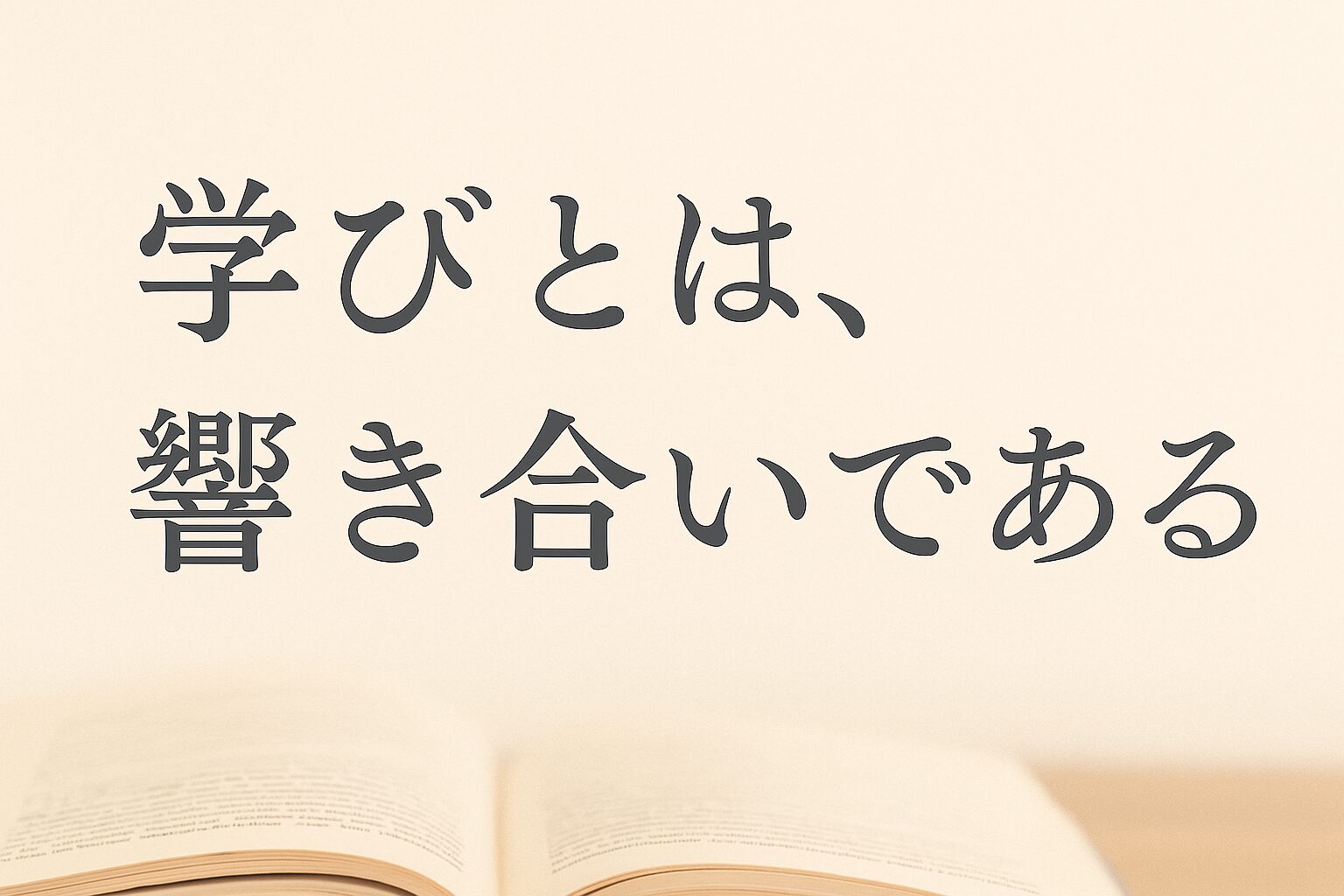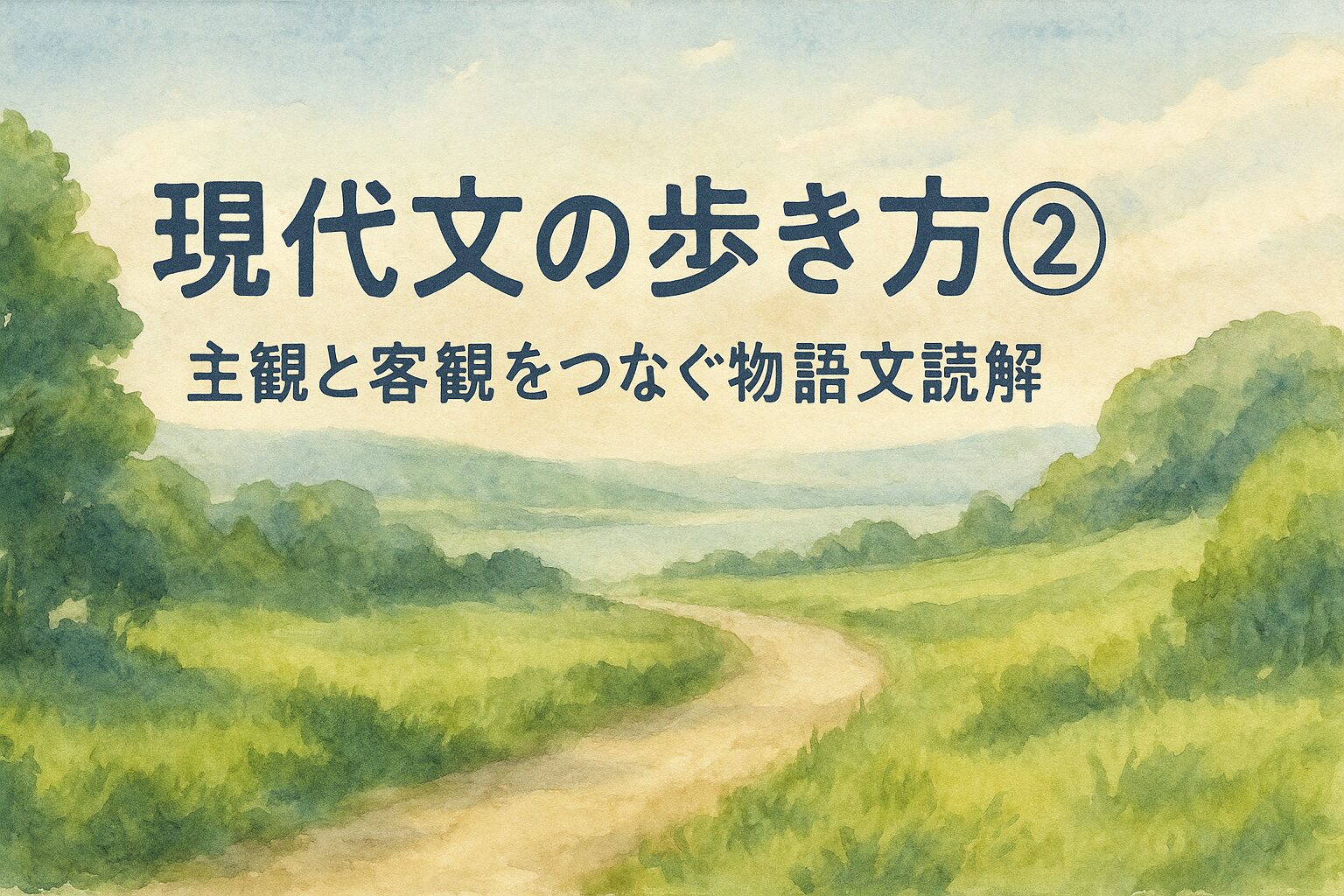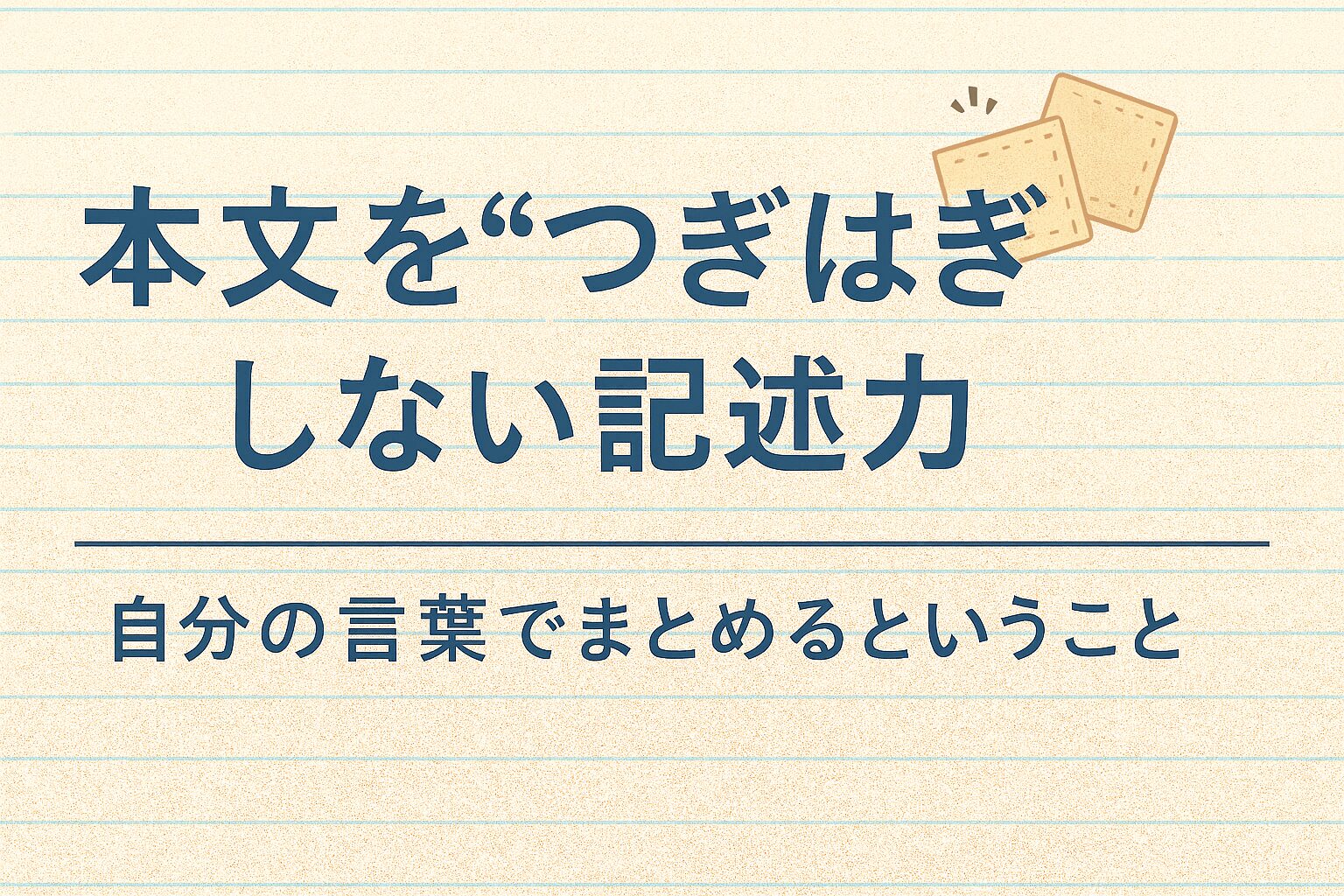国語が教えてくれる【対話】という営み
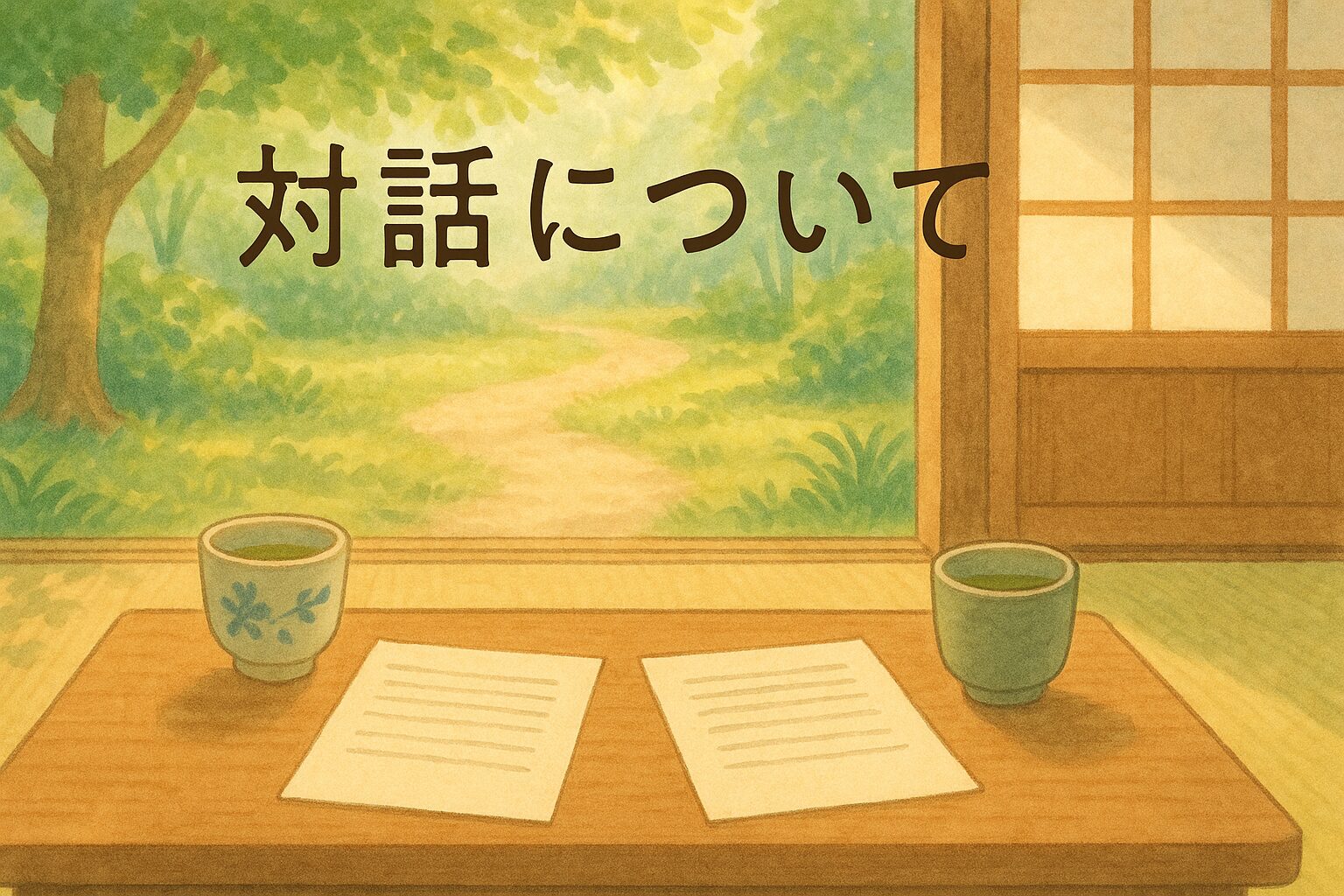
国語は学校の授業や受験のための科目として学習するものにとどまりません。
ただ答えを出すだけでなく、文章や自分自身と向き合う時間が生まれます。
そこには
- 文章との対話
- 自分自身との対話
が必ず含まれるため、国語に取り組むことでおのずと広義での「対話」の力が身につきます。
さらに澪日荘では、以上に加えて1対1の対話を重視しています。
文章との対話
国語の学習においては、説明文・評論文や近代・現代の小説、古典、エッセイその他「読む」対象となる材料を使います。
他の記事でも触れていますが、文章を読む際には、その文章のいわば文字面をまず正確に把握し、そこから文脈や文章の流れ、雰囲気、書き手の属性や考え方など総合的に、読み手は感じ取っています。
無意識であるにせよ、そのような読み方ができなければ、文章を読んでいるとは言えないかもしれません。
誰かと話をするときも、相手の表情や声色、そのときの調子、立場などを自然と感じ取って話すものです。
他者と話すことはまさに「対話」ですから、国語を学ぶことは文章との対話であり、そのまま普段の対話へ繋がっていることになります。
自分自身との対話
上で挙げたような読む対象に触れると、意図しなくともさまざまな思考や感情が生まれてきます。
書き手の意見に賛成したり、納得がいかなかったり、気に入らないけど説得的だと感じたり、やっぱりおかしいよなと思ったりします。
このとき、教科書会社や文章の書き手に手紙などを送り「○○の点がおかしいです」と主張する強者もいるかもしれませんが、多くはそこまで至りませんし、それで然るべきでしょう。
文章の書き手は紙や手続きやフィルターを何層も隔てた向こう側にいるのだから、自分が思ったり感じたりしたことは、第一に自分自身が扱うもののはずです。
その文章に触れ、どうして自分がそのように思い、感じたのかを自分自身で理解することが求められる場が国語には元々用意されているのです。
これは自分自身との対話に他なりません。
1対1の対話
澪日荘では、ここまで見たような国語という科目そのものによって生まれる「対話」を、1対1の人間同士の場に移行させることで深めていきます。
1対1ですから、どちらかが話していれば他方は聴き、その立場が逆転し、という循環が成立します。
聞き流してもOKという条件でないからこそ、互いにより深く広く話すことができ、思いがけないものの発見に至ることがあると考えています。
具体的にどのような対話をおこなうかについて、簡単に触れておきます。
授業の流れによって取り上げる内容はいろいろですが、たとえば以下のようなものがあります。
- 文章素材
- 生活
文章素材
国語(や小論文、英語)の授業をしていますから、そこで出てきた文章や素材について話をすることはもちろん多いです。
ただ、このとき答えや解説の内容に対して、生徒さんなりにどう考えるかをよく尋ねるようにしています。
記述問題などで特に顕著ですが、参考書や問題集の解答例以外にも適切と考えられる答えが存在することは経験上確実です。
生徒さんと一緒によりよい答え方がないかどうかを検討する中で、何がその問題の要点なのか、ひいてはその文章自体の根幹はどこにあるかなどを見出す努力をします。
生活
教科書などに載っている文章の書き手や、生徒さん、私自身、さらにどんな人も、これまでの環境・経験や現在の生活から成り立ってきた存在です。
ですから、たとえ学業面だけに絞って何らかの成果を求めるという場合であっても、生徒さんの日常生活に触れないわけにはいきません。
どんな趣味があって、好きで観ているYouTubeチャンネルは何で、好物は何で、学校やお家ではこんなことがよくて悪くて嫌で……
この部分は私個人の楽しさになってしまうかもしれませんが、お子さん・生徒さんの多様さは目を見張るものがあります。
表面上は「普通」(?)のような顔をしていても、話をしていくと思いもよらない趣味を持っていたり、大人顔負けの広い視野で物を見ていたり、それでいてどこか抜けていたり。
本人が誰かに話すものではないと思っている場合もあって、特にそういう生徒さんには自身の可能性の豊かさや特質を実感してもらうべく、積極的におしゃべりをしています。
国語の可能性は無限
以上のように、国語科は人間としての人が、人格を持って力と意を注ぎ練り上げた文章や素材を扱いますから、狙わずとも「対話」が生まれる環境が得られます。
どのくらい読み込んだり、感じ取ったりするかによって自分が拓かれていき、自身が拓かれるとまた素材や対話における理解度が増すので、そこに限界がありません。
この意味で、大きく言えば国語は未来を創る科目なのではないかと考えています。