第五話:「教わることと、自分のやり方を見つけること」
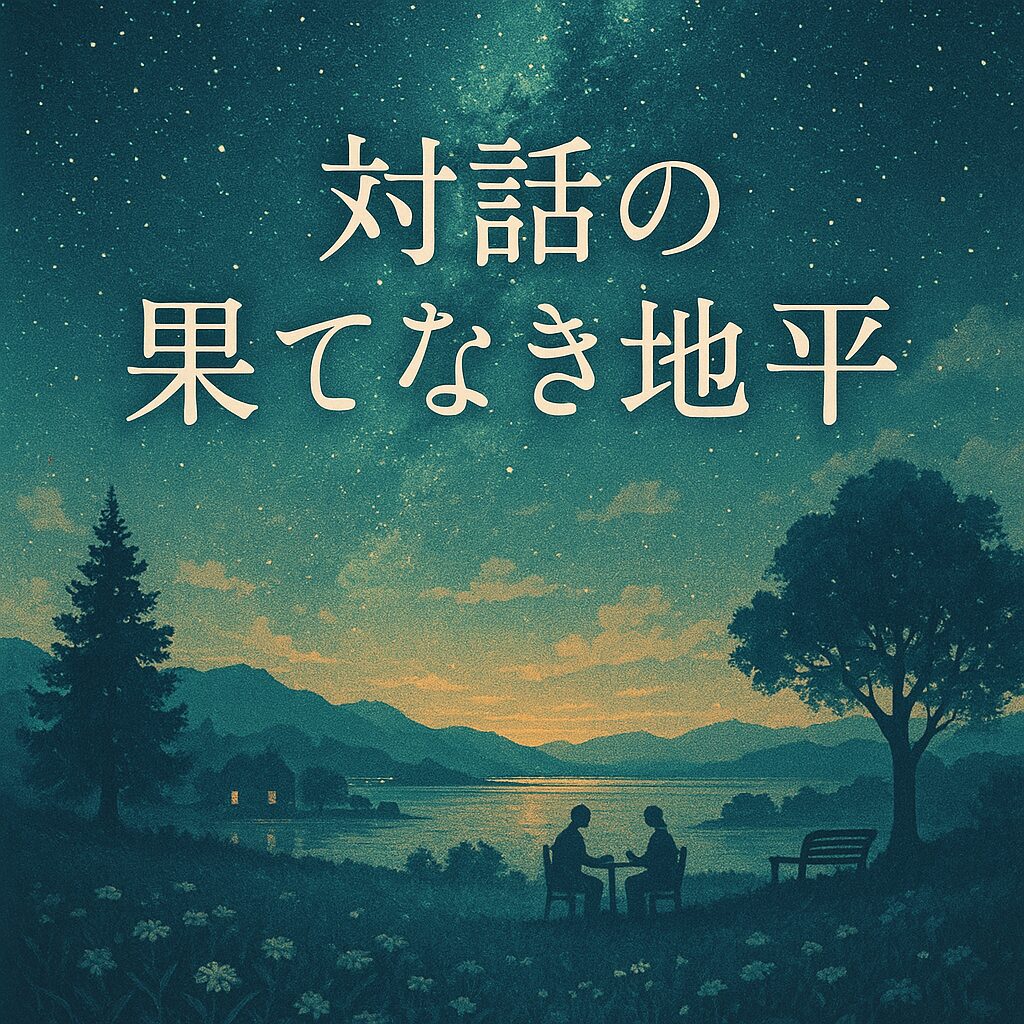
本連載は、日々の対話やふと立ち止まる瞬間に
生まれた問いをもとに
AIとの応答を通して綴った記録です。
「ことばの手前」にある感覚や沈黙にも
意味が宿ると感じています。
やりとりを重ねるうち“何か”が浮かび上がる様子を
見守っていただけたら幸いです。
第5話|学びのかたち・心のはたらき
「教えてもらえれば、自分にもできるのに」
そう思うのは、ごく自然なことです。でも、ときにその思いが、かえって自分を縛ってしまうこともあります。
やり方を教えてほしい、正解が知りたい——そんな気持ちの奥にあるのは、自分の手で何かをつかもうとする願いかもしれません。
教わることと、自分で見つけていくこと。そのあいだにある揺らぎを、丁寧に見つめてみました。
「やり方を教えてほしいんです」
その生徒は、自分の特性についても率直に語ってくれる。
「アスペルガーだから」という言葉を、自分の理解の補助線として使っている。
それが閉じたレッテルではなく、苦難を引き受ける方法として語られていることは、十分に伝わってくる。
でも、そこに少しだけ、何かが引っかかる。
「やり方を教えてもらえれば、自分にもできる」
たしかに、うまく噛み砕かれた説明があれば、突然に理解が進むこともある。
ただ、その前提にずっと依拠してしまうと、
「やり方が外にある」「それを得ればできる」という構図から抜け出せなくなってしまうのではないか。
教え方を工夫することは、もちろん必要だ。
でも、それだけでなく「自分で自分のやり方を発見すること」にも、学びの意味を置きたい。
たとえば、彼が「これはこうすればできるんだ」と腑に落ちたとき、
それがどれほど丁寧に説明された結果だったとしても、
実際には彼自身が、その説明を自分に合った形で受け取り、応用し、理解の型を作っている。
そのことに、もっと光を当てたい。
「教わったからできた」のではなく、「教わったことを、自分なりに受け取ったから、できた」のだ。
きっと、彼はそれをすでに体験している。
ただ、「外から与えられること」の印象が強く残っているだけかもしれない。
「やり方を示してほしいのに、一緒に考えようとされてる」
彼の言葉に、ほんの少しの困惑と、苛立ちと、願いとが混じっていたようだった。
でも、その「一緒に考える」時間のなかでこそ、
自分だけの方法が、少しずつ立ち上がってくる可能性がある。
「うまくできる」ためのやり方ではなく、
「やってみよう」と思えるための土壌を耕す。
そのとき、たとえ外側からのやり方に頼るとしても、
それを受け取る本人の在り方こそが、学びを決定づけている。
その本人の在り方に、寄り添いたい。
📘note連載でも公開中です
この対話記録は、noteでも連載しています。
ページのレイアウトやコメント機能など、読みやすい形でご覧いただけます。
よろしければ、こちらもあわせてお楽しみください。
👉 note連載「対話の果てなき地平」へ
