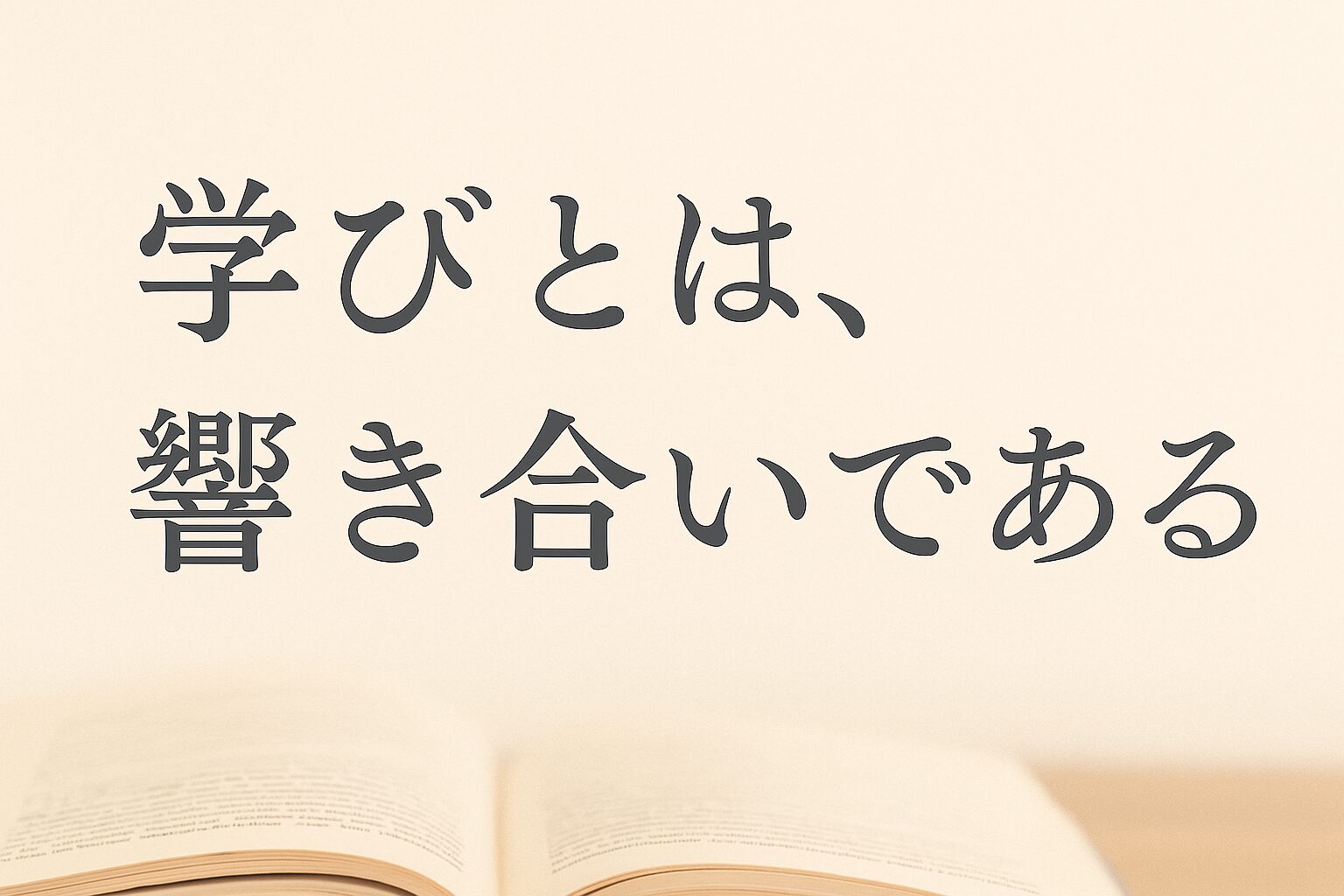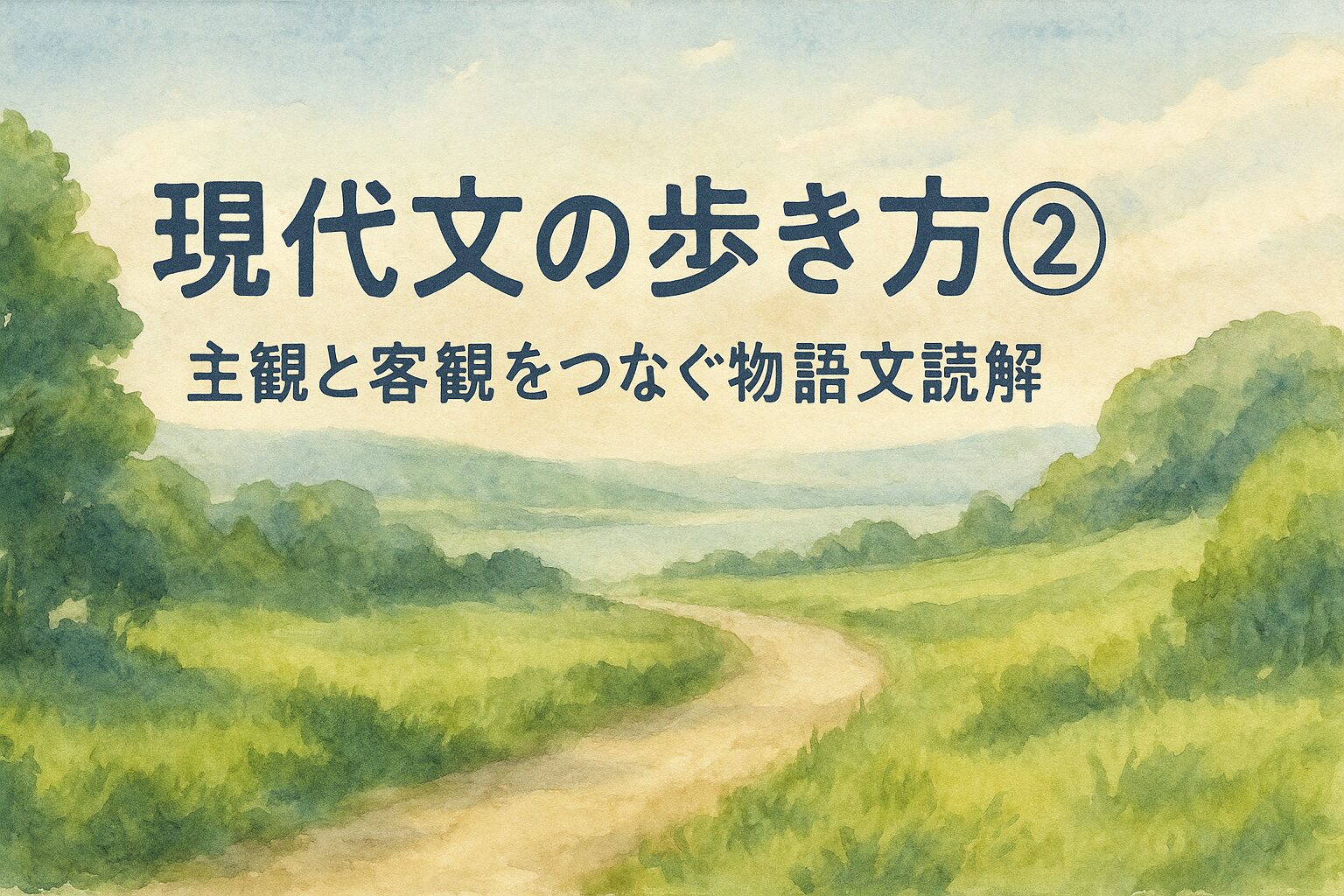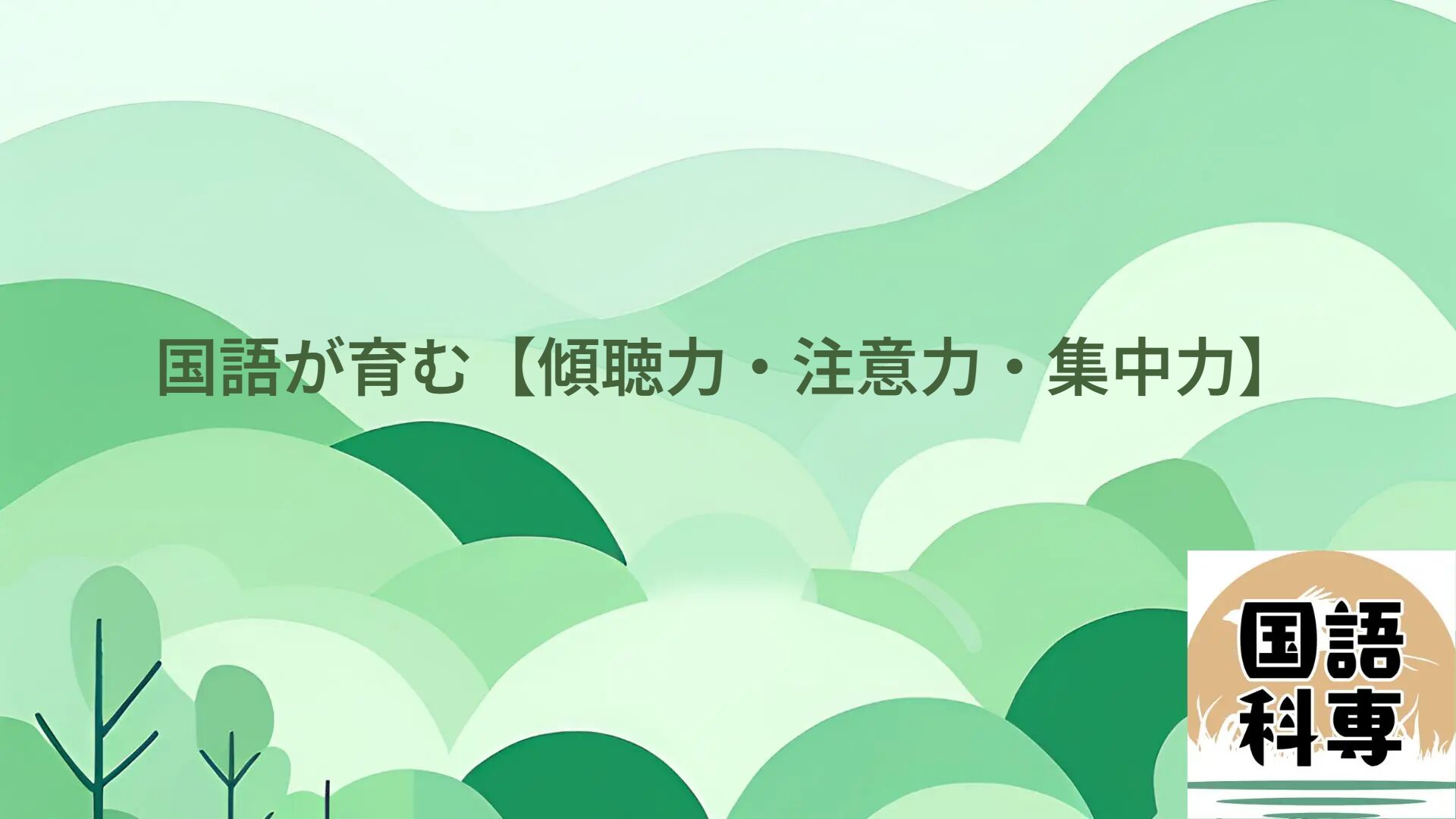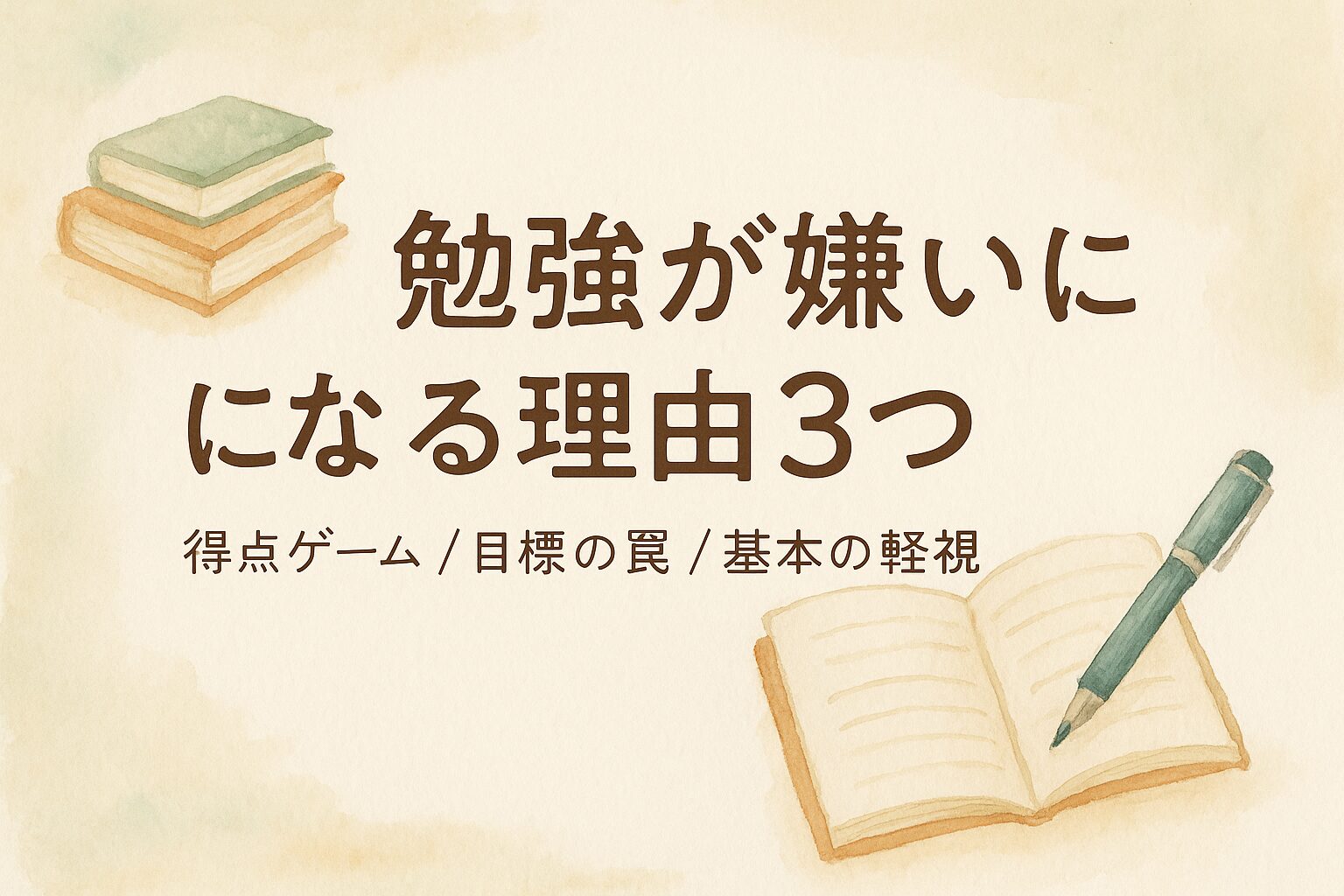自分の生活から始まる学び──“勉強嫌い”という言葉の奥にあるもの

「勉強がとにかくキライ」という言葉を耳にします。
食べものや映画などは、嫌いなものはただ嫌いでかまわないのに、どうして勉強にはそこまで「キライ」と言わせ、勉強自体を拒否させる力があるのでしょうか。
さらに「勉強がキライ」はときに自己否定感までもともなうのはなぜなのでしょうか。
“学び”のあり方から見てみようと思います。
学びが「教科」という箱に閉じ込められる
小さいころは誰でも目に映るもの、手に触れるものが新鮮で、どんなことでも学び取っています。
物の名前や文字の書き方、お父さんお母さんの言葉遣いなど、学ぶ対象に制限がありません。
ところが、広い意味で学校(勉強をするところ)へ入学する段になると、その限りない“学び”が急速に「箱」に入ります。
成長して人格を形成し、社会に出て道を歩んでいくための土台作りの時期ですから、定められたカリキュラムや理念に基づいて、一定の教育・教授内容や方法が採用されることは仕方がないでしょう。
その一方で、「算数」とか「社会」とか、ひとつの名前のもとに組織だてられた学習内容を扱わざるを得ないことから、学びはその範疇でおこなわれがちになります。
同時に達成度の計測が必要となるので、テストや実技・実習などで点数をつけていきます。
点数と評価がゴールになったとき
教科・科目という箱と、どのくらい達成できたかという点数により、学びはある意味で目に見えやすくなります。
その箱にたくさん入っているほうが偉くて、あまり入れられていないのは良くない。
箱の使い方が上手な方が評価されて、下手なのは望ましくない。
こうした知識量やその使い方の上手下手、一番分かりやすい得点などが、それ自体で目的化してしまうことは必然といえるでしょう。
しかし、本格的なAI時代に突入し、これら単体での意義は相対的に低下します。
現代のこうした構造の中で、どうしても「勉強がキライ」+「できない自分がキライ」になることがあるのは、当たり前なのかもしれません。
学びはより繊細かつ広く、深い
本来はこれまでも同様だったのですが、“学び”がもっと繊細で広く、深いものであることを再確認する必要があると思います。
例えば、
- 知識獲得にとどまらず、相互の連関・背景を理解し、結び付けて考える力
- 個々人の性質・特性により“学び”はいろいろであること
などを、私たちは認識する必要があるのではないでしょうか。
とりわけ後者について、上に述べたような教科の学習では、学ぶべき内容が先に提示されていて、それを身に着ける学習をし、到達度を測るというやり方がなされていました。
けれど、個人の特質に応じた多様な能力が、それぞれ程度も方向性も異なるものであるならば、同じ内容を学ぶ際にも無限に方法があるはずです。
学びと個々人の性質とが本当は不可分であることが、意識されてきていると感じています。
自分の生活から始まる学び
“学び”が個人の特質と繋がっていることを確認できて初めて、冒頭で挙げた幼いころの体験が復活する可能性があります。
どんな事柄を学ぶにしても自分自身の性質を考慮するということは、普段の自分の生活が学びの場であることと同義です。
毎日の生活は生きることそのものですから、ここへ来て“学び”の射程は無限であることが分かるというわけです。
翻って、上で「箱」と呼んだ科目の学習も、このような自分が生きることそのものという射程の中に位置付ければ、自分なりの学びに転換・昇華できると考えています。
そのとき、学びは“やらされること”から、“自分のもの”へと変わっていきます。